「文章を読んでも内容が頭に入らない」「ただ読んでいるだけで、意味がわかっていない気がする」——
そんなお子さんの姿に、不安を感じているママやパパも多いのではないでしょうか?
最近はスマホや動画の普及により、“文字を読む時間”が減っている子どもが増えています。その影響で、以前よりも読解力が育ちにくい環境になっているのが現状です。
でも、読解力は生まれつきの才能ではなく、日常の中でも少しずつ育てていける力です。親子の会話や読書の時間など、ちょっとした日常の工夫でぐんと伸ばすことができます。
この記事では、元国語教師ママの視点から、読解力が伸び悩む原因や家庭でできる5つのステップ、読解力が身につくことで変わる子どもの姿をわかりやすく解説します。
「読むのが苦手…」から「読むのが楽しい!」へ。おうちでできる“読解力アップ”のヒントを、一緒に見つけていきましょう。
「そもそも国語力を育てるためには何から始めればいいの?」と悩まれている方には、まずこちらの記事をチェックしてみてくださいね!
▶【関連記事】「【小学生~中学生向け】国語力を育てたいけど、何から始めればいい?“タイプ別”おすすめステップ」
子どもの読解力が伸び悩む原因とは?
「読んでも内容がよくわかっていない」「ただ読んでいるだけ」という子が増えている背景には、いくつかの環境的な要因があります。
ここでは、現代の子どもたちに多く見られる読解力低下の原因を見ていきましょう。
スマホや動画中心の生活で「読む量」が減っている
スマホやタブレットで動画を見る時間が長くなっていませんか?
YouTubeやショート動画、アニメなど、子どもにとって動画は楽しく夢中になれるもの。ちょっと休憩のつもりが、気づけば1時間以上経っていた…という経験、きっと多くのご家庭にあるのではないでしょうか。
動画は“見ているだけで理解できる”のが魅力ですが、その反面、「言葉を使って考える力」をあまり使わずに済んでしまうという特徴もあります。
一方で、本を読むときは「どんな場面かな?」「この人はどう思っているんだろう?」と頭の中で想像したり、内容を整理しながら理解したりします。こうした「想像しながら読む時間」こそが、読解力を育てる上でとても大切な経験なのです。
もちろん、動画にも良い面はたくさんあります。知識を広げたり、興味のきっかけになったりと、うまく活用すれば学びにもなります。ただ、受け身で見る時間が長くなると、“文字を追って考える”習慣が減ってしまい、読解力の土台が育ちにくくなることもあります。
つい見すぎてしまうときは、「動画は1日30分まで」「寝る前は絵本タイムにしよう」など、親子でルールを決めるのがおすすめです。「見ちゃダメ!」と制限するよりも、「見る時間」と「読む時間」のバランスを意識することが大切。
少しずつでも“文字を読む時間”を意識的に増やしていくことで、自然と読む集中力や文章の流れをつかむ力が育っていきます。
SNSや短文文化で“正しい日本語”に触れる機会が減っている
最近の子どもたちは、SNSやチャットで友達とやり取りすることが増えていますよね。
スタンプや絵文字、短い言葉や略語などで気持ちを伝えられるため、「便利で楽しい!」と感じるのも自然なことです。しかし、その一方で“正しい日本語”に触れる機会が少なくなっているのも事実です。
SNSでは、「てにをは(助詞)」や文のつながりを意識せずに、感覚的なコミュニケーションが中心になります。例えば、「ヤバい」「それな」などの短い言葉で感情を表現することが多く、詳しく説明したり、自分の考えを整理して話したりする機会が少なくなっています。その結果、「自分の気持ちを言葉で表現する力」や「状況を正しく伝える力」が育ちにくくなってしまうのです。
もちろん、こうした表現が悪いというわけではありません。友達との距離が縮まったり、楽しい気持ちを共有できたりする良い面もたくさんあります。
ただ、“短文文化”だけに慣れてしまうと、作文や読書感想文など、「言葉で伝える力」が求められる場面でうまく表現できないという悩みにつながりやすくなります。
そこで、家庭では、子どもの言葉を引き出すような会話を意識してみましょう。例えば、「ヤバかった!」で終わらせずに、「どんなところがヤバかったの?」「それって楽しかったの?びっくりしたの?」と、一言掘り下げて聞いてみるのです。
そんなやり取りを積み重ねることで、子どもは自然と“自分の気持ちを言葉で表現する練習”ができ、読解力や表現力の土台を家庭の中で少しずつ育てていくことができます。
人との関りが減り、“考えを伝え合う”経験が少なくなっている
コロナ禍をきっかけに、外で友達と遊んだり、顔を合わせて話したりする機会がぐっと減りましたよね。今ではオンラインでの交流やSNSでのやり取りが中心になり、人と直接会話する時間が少なくなっている子も多いのではないでしょうか。
実は、読解力というのは“人とのコミュニケーションの中で育つ力”でもあります。誰かと話すとき、「相手はどう思っているんだろう?」「自分の考えをどう言えば伝わるかな?」と自然に考えますよね。こうした「相手の気持ちを想像する力」や「自分の考えを整理して伝える力」こそ、文章を理解するときにも欠かせない土台になるのです。
反対に、人と関わる機会が減ると、言葉を使ってやり取りする経験も減り、結果として“文章を自分ごととして理解する力”が育ちにくくなってしまいます。つまり、日常生活で「相手の気持ちを考える」「自分の考えを伝える」といった経験が少ないほど、読解力の伸びにも影響が出やすいのです。
また、最近では、SNSなどで“同じ趣味や価値観を持つ人だけ”とつながる傾向も強まっています。共通の話題で盛り上がれるのは楽しいことですが、実は「違う考えを持つ人」と話すことこそが、考え方の幅が広げ、言葉で説明する力を育てる貴重な機会になります。
だからこそ、家庭の中では「どう思う?」「もし自分だったらどうする?」といった問いかけを意識的に取り入れてみましょう。日常の中で、親子でゆっくり会話を重ねることが、子どもの“自分の言葉で考え、相手の気持ちを想像する力”を育てていきます。それこそが、文章を深く理解し、登場人物の気持ちを読み取る力につながっていくのです。
読解力が低いとどんなことに困る?|学習や生活への影響
「読解力が大切なのはわかるけど、実際にはどんなところで困るの?」
そう感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
読解力は勉強面だけでなく、日常生活にも大きく関係しています。人の話を正しく理解したり、自分の気持ちを言葉で表したりする力も、実は読解力と深くつながっているのです。
ここでは、読解力が低いとどんな場面で困るのかを、具体的に解説します。
文章問題やテストの意味がつかめない
「問題を読んだのに、何を聞かれているのか分からない…」
「ちゃんと勉強しているのに、テストで思うように点が取れない…」
そんな場面に心当たりがある、というご家庭も多いのではないでしょうか。
実はこれ、「勉強していないから」や「集中していないから」ではなく、“読解力”がまだ十分に育っていないことが原因のことが多いのです。
読解力が低いと、文章の中で「誰が」「何をしているのか」といった主語と述語の関係や、「何を問われているのか」という意図を正しくつかむのが難しくなります。そのため、算数の文章問題や理科の実験説明などでも、内容をうまく整理できずに混乱してしまうことがあります。
また、近年のテストでは、“自分で考えて説明する力”を問う問題が増えています。単に暗記するだけではなく、「なぜそうなるのか」を文章から読み取り、自分の言葉で説明する力が求められるようになっているのです。読解力が低いと、せっかく知識があっても、それを十分に発揮できず、惜しい結果になってしまうこともあります。
親としては、「理解しているはずなのに点が取れない」「問題文を最後まで読めばできるのに」と感じることもありますよね。でも、これは集中力の問題ではなく、言葉を整理して理解する力がまだ発達途中なだけ。焦る必要はありません。
大切なのは、「どうしたら問題文の意味をつかめるようになるか」を一緒に考えていくことです。たとえば、家庭で日常的に「この問題、どんなことを聞かれていると思う?」「どういう意味かな?」と声をかけてみるだけでも、子どもが文章の意図をつかむ練習になります。
こうした日々の積み重ねが、やがてテストや文章問題にも自信を持って取り組める力につながっていくのです。
読書や勉強への苦手意識が強くなる
「文章を読んでも、何を言っているのか分からない…」
そんな経験を繰り返しているうちに、子どもは少しずつ「読むのが苦手」「本ってつまらない」と感じるようになってしまいます。
特に小学生の時期は、「読めない=できない」「できない=嫌い」と感じやすく、一度苦手意識が芽生えると、自分から本を読んだり、勉強に取り組んだりする意欲が下がってしまうことがあります。
また、読解力が十分に育っていないと、授業中に先生の説明を聞いても理解しづらかったり、教科書の内容が頭に入りにくかったりすることもあります。そうなると、「分からないから面白くない」「どうせやってもできない」という悪循環に陥ってしまうことも。
親としては、「もっと本を読んでほしい」「勉強を嫌がらないでほしい」と思いますよね。でも、子どもにとって“読めないものを読む”のは、大人が想像している以上にとても大変なこと。無理に「読みなさい」と言うよりも、まずは“読める・分かる”経験を積ませてあげることが大切です。
例えば、短い絵本やマンガ、図鑑など、子どもが興味を持てそうなものから始めてみましょう。内容を理解できたときの「読めた!」「分かった!」という小さな成功体験が、「読むって楽しい」という気持ちを育ててくれます。
そして、少しずつ読解力がついてくると、文章の意味を理解できるようになり、「なるほど、こういうことか!」と感じられる瞬間が増えていきます。こうした“理解できた喜び”が積み重なることで、「知るって楽しい」「もっと読んでみたい」という前向きな気持ちにつながり、勉強全体への意欲も自然と高まっていくのです。
読解力は、テストの点を上げるためだけの力ではなく、“学ぶことを楽しむ力”そのもの。親子で一緒に小さな成功体験を積み重ねながら、「分かるって楽しい!」という感覚をたくさん味わわせてあげたいですね。
将来の“考える力”“伝える力”にも影響する
読解力は、テストの点数を上げるためだけの力ではありません。
実は「考える力」や「伝える力」など、将来にわたって役立つ“生きる力”の土台になっています。
例えば、人の話を聞く時には、相手の言葉の意味を正しく理解しようとしますよね。これはまさに“読解力”と同じ力。言葉の背景や意図を汲み取る力があると、相手の気持ちを想像したり、自分の考えを整理して言葉にしたりすることが自然とできるようになります。
逆に、読解力が低いと、相手の話を誤解して受け取ったり、自分の意見をうまく言葉にできなかったりすることもあります。こうした「理解」や「表現」のつまずきは、子ども時代だけでなく、大人になってからも影響します。
社会に出ると、「説明を正しく理解する」「自分の考えをまとめて発表する」「報告書やメールで伝える」といった場面がたくさんあります。これらのすべてに共通して必要になるのが、“言葉を通して考える力”、つまり読解力なのです。
もし、この力が十分に備わっていなければ、仕事の指示をうまく理解できなかったり、誤解が生じて人間関係に悩んだりと、社会生活で困ることも少なくありません。
つまり、読解力を育てるということは、単に国語の成績を上げるためではなく、「相手の考えを理解する力」「自分の意見を言葉で伝える力」「状況を整理して判断する力」といった、社会で生きていくための基礎を育てることにもつながります。
読解力は一朝一夕で身につくものではありません。日々の会話や読書、身近な出来事の中で少しずつ積み重ねていくことで、子どもは“考える力のある大人”へと成長していきます。
読解力を育てることは、未来の「伝える力」や「生きる力」を育てること。毎日の小さな“言葉のやり取り”こそが、子どもの将来を支える大きな力になるのです。
家庭でできる!読解力を伸ばす5つのステップ
読解力は、ただたくさん本を読むだけで自然に身につくものではありません。大切なのは、読むことを通して、子どもが自分で考えたり、感じたり、言葉で表現したりする経験を積み重ねていくことです。
家庭でも、ちょっとした声かけや読み方の工夫をするだけで、子どもの理解力はぐんと伸びていきます。
ここでは、毎日の生活の中で無理なく取り入れられる“読解力アップの5つのステップ”をご紹介します。
①読書習慣をつける
読解力を育てるための第一歩は、「毎日ほんの少しでも、本に触れる時間をつくること」です。たとえ1日10分でもかまいません。短い時間でも続けることで、“読むこと”が生活の一部になっていきます。
読書が苦手な子には、最初から長い本をすすめる必要はありません。絵本・マンガ・図鑑・児童書など、子どもが「読んでみたい」と思えるものから始めましょう。大切なのは“読むことを楽しむ”ことです。好きなジャンルの本を自由に選ばせてあげると、「読む=楽しい」という感覚が自然と身に付きます。
また、親子で一緒に読む時間を持つのもとても効果的です。「今日の本はどんなお話だった?」「この絵、面白いね!」など、感じたことを言葉にしながら読むだけで、本の世界がぐっと広がります。
よく「絵本の読み聞かせ中は、物語に集中させて、余計な話はしない方がいい」と聞くことがありますが、実はそんなことはありません。むしろ、「これ、うちの犬みたい!」「このうさぎさん変な顔してる!」といった子どものつぶやきや発見こそ、読書を“自分ごと”として楽しめている証拠です。そんな瞬間は「そうだね」「おもしろいね」と受け止めて、一緒に笑ったり考えたりしながら読むことで、子どもの想像力や言葉への興味がぐんと広がります。
さらに、読む時間を決めておくのもポイントです。夜寝る前や朝ごはんのあとなど、1日の中に“本を読む時間”を読み込むことで、読書が自然と習慣になっていきます。
そしてもうひとつ大切なのが、親が本を読む姿を見せること。子どもは、親の背中をよく見ています。パパやママが本を読んでいると、「本っておもしろそう」「自分も読んでみたい」と感じるものです。
「おうちに本がある」「家族が本を楽しんでいる」——そんな環境こそが、子どもの読解力を育てる一番の土台になります。
②読む前と後に「予想」と「感想」を話す
読解力を伸ばすために大切なのは、“ただ読む”のではなく、“考えながら読む”習慣をつけることです。そのためにおすすめなのが、本を読む前と読んだ後に、親子でちょっとした会話をすること。
例えば読む前には、「このタイトルを見て、どんなお話だと思う?」「どんなことが起こりそう?」などと、“予想”を立ててみましょう。こだれけで、子どもは「この後どうなるんだろう?」と想像しながら読むようになり、自然と物語の内容に集中力できるようになるのです。
そして読み終えた後には、「どんなところが面白かった?」「思っていたのと違った?」と“感想”を話す時間を持ってみてください。ここで大切なのは、答えを求めないこと。どんな感想でも「なるほど、そう思ったんだね」と受け止めてあげることで、子どもは安心して自分の考えを話せるようになります。
この“読む前の予想”と“読んだ後の感想”を繰り返すだけで、子どもは自然と“考えながら読む”習慣を身に付けていきます。さらに、読んだ内容を自分の言葉で説明することで、理解が深まり、文章の流れを整理する力も育ちます。
- 「主人公はどんな気持ちだったと思う?」
- 「もし自分がこの人だったらどうする?」
- 「このお話の中で一番印象に残ったところはどこ?」
小さなお子さんの読み聞かせ中の声かけについて詳しいことが知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてくださいね!
▶【関連記事】「【年齢別】読み聞かせがもっと楽しくなる!絵本好きになる声かけのコツ5選」
こうした会話を通して、子どもは物語を“読む”だけでなく、“感じて考える”ようになります。また、登場人物の気持ちを想像することは共感力を育て、自分の考えを言葉にすることで表現力も磨かれていきます。
親子で「読む・話す・聞く」をセットにした時間を作ることで、本を読むことがより深い学びの時間に変わります。「なるほど、そういうことか!」と子どもが感じる瞬間を、ぜひ一緒に楽しんでみてください。
③物語・説明文などさまざまなジャンルに触れる
読解力をバランスよく伸ばすには、いろいろな種類の文章に触れることが大切です。
例えば、物語文は「登場人物の気持ちを想像する力」や「気持ちの変化を読み取る力」を育ててくれます。一方で、説明文は「情報を整理して理解する力」や「理由や因果関係を考える力」が身につきます。
このように、物語と説明文の両方を読むことで、「感情を読み取る力」と「論理的に考える力」がバランスよく育ち、総合的な読解力につながっていくのです。
とは言っても、子どもによって得意・不得意なタイプの文章は違いますよね。物語は好きでも説明文が苦手、図鑑は好きだけどお話は読まないなど、偏りがあるのは自然なことです。そんなときは、無理に苦手分野を押し付けるのではなく、好きなジャンルから少しずつ広げていくのがコツです。
- 物語が好きな子なら:登場人物の体験をもとにしたノンフィクション本へ
- 動物図鑑が好きな子なら:動物の生態を説明する読み物やコラムへ
このように、興味の延長線上で少しずつ新しいジャンルに触れさせると、自然に世界が広がっていきます。
また、新聞の子ども向けコーナーや、身近なニュース記事を一緒に読むのもおすすめです。時事的な内容を通して、「なぜこうなったのか?」「自分だったらどう思う?」と会話を交わすことで、文章を理解するだけでなく、“自分の頭で考える力”も育っていきます。
大切なのは、「この本を読まなきゃ」と思わせないこと。「いろんな本に出会うのって楽しい!」という気持ちを持てるように、親が温かくサポートしてあげましょう。
物語・説明文・詩・図鑑・新聞など、いろんなジャンルの文章に触れることで、子どもは自然と“言葉の世界の広さ”を感じ取るようになります。その積み重ねが、読解力の大きな成長につながっていくのです。
④要約の練習で“理解の深さ”を確認する
読解力を高める上でとても効果的なのが、「要約」です。要約とは、文章を読んだあとに「この文章の中でいちばん大事なことは何か」を自分の言葉で短くまとめること。つまり、内容を正しく理解していなければできない“読解力の証”なのです。
物語文なら「主人公がどんな気持ちで、どんな行動をしたのか」、説明文なら「筆者が一番伝えたかったこと」を1~2行でまとめるようにすると、理解の深さを自然に確認できます。
とは言え、いきなり上手にまとめるのは難しいもの。最初は次のような流れで、少しずつステップアップしていくのがおすすめです。
①登場人物や出来事を整理する
まずは、「だれが」「どんなことをしたのか」をシンプルに言葉にしてみましょう。
例:「ゆうたが友達とけんかをした」「ねこが友達を探していた」
→ここではまだ“短くまとめる”ことを意識しなくてもOK!話の流れをつかむ段階です。
②いちばん大事な場面や気持ちを選ぶ
次に、「このお話で一番大事なところはどこ?」「主人公はどんな気持ちだった?」と考えてみましょう。
例:「けんかしたけど、話し合って仲直りできたところ」「ねこに友達ができてうれしそうにしていた」
→このステップで、子どもが自分なりに“中心”を見つけることが大切です。
③大事な部分を1~2文でつなげる
最後に、①と②をもとにして1~2文でまとめてみます。
例:「ゆうたは友達とけんかをしたけれど、話し合って仲直りできた話」
→完璧に短くなくてもOK!“内容を整理して伝える”ことができれば立派な要約練習です。
親子で「この話の大事なところってどこだったと思う?」と話し合うのもおすすめです。お互いの考えを言葉にすることで、「なんとなく読んだ」ではなく、「理解して整理する」読書へと変わっていきます。
要約の力は、国語のテストだけでなく、自分の考えを整理して伝える力にもつながります。毎日の読書のあとに、“ひとこと要約タイム”を取り入れて、考える読書を習慣にしてみましょう。
⑤辞書を使って語彙力をアップする
読解力を育てるうえで欠かせないのが「語彙力」です。
言葉をたくさん知っているほど、文章の意味を正しく理解し、自分の考えを表現する力も育っていきます。
語彙力を伸ばすには、ただ“読書量を増やす”だけで不十分です。大切なのは、わからない言葉に出会ったときに、辞書で調べる習慣をつけること。
たとえば、読書中に「これ、どういう意味?」と子どもが聞いてきたら、「一緒に辞書で調べてみよう!」と声をかけてみてください。意味を調べたあとに、「この言葉、どんなときに使えそう?」と話してみると、意味がしっかりと身に付きます。
①調べた言葉を使ってみる
辞書で調べて終わりではなく、その言葉を実際に使うのがポイントです。「今日は“挑戦”って言葉を使ってみようか!」と、日常会話の中に取り入れてみましょう。
②“自分専用の言葉ノート”を作る
調べた言葉をノートに書き溜めておくのもおすすめです。「言葉・意味・使い方」をセットで書くと、あとで見返したときにすぐ思い出せます。
③絵や例文でイメージをつける
特に小学生のうちは、文字だけで覚えようとすると難しいこともあります。「“努力”って、たとえば練習を毎日がんばることだよね」など、実際の行動や身近な例を一緒に考えてあげましょう。
最近の子ども向けの辞書は、イラストや豆知識が豊富で、調べるのが楽しくなる工夫がいっぱいです。
わが家の小学生の息子が愛用している辞書(小学校低学年向け)
小学校中学年以降はこちらがおすすめ
辞書を“勉強の道具”ではなく、“言葉を探す宝さがしツール”として使えるようになると、子どもの読解力もどんどん広がっていきます。
言葉を知ることは、世界の見え方を豊かにすること。日々の「調べて、使って、話す」体験の積み重ねが、確かな読解力へとつながっていきます。
日常の中で楽しく語彙力を育てたい方は、こちらの記事もチェックしてみてくださいね!
▶【関連記事】「おうちでできる!語彙力アップの簡単遊び5選」
読解力が身につくと、勉強も日常も変わる!
読解力が育つと、単に“国語が得意になる”だけではありません。子どもが自分で考え、理解し、伝える力がつくことで、勉強の理解度や日常生活そのものが変わっていきます。
ここでは、読解力が身に付いた子どもがどんなふうに変化していくのか、3つのポイントを詳しく解説します。
国語以外の教科理解もスムーズになる
読解力はすべての教科の土台になる力です。
算数の文章問題や理科・社会の説明文、英語の長文など、どの教科でも「書かれていることをを正しく理解する力」が求められます。
たとえば、算数で「りんごが3個ずつ入った袋が5つあります。全部で何個ありますか?」という問題を解くとき。もし「3個ずつ」と「5つ」という関係を正しく読む取れなければ、計算の式を立てることすらできません。
理科や社会でも「なぜそうなるのか」「どんな仕組みなのか」を説明する文を理解する力が必要です。
つまり、読解力があると、「問題の意味を正しくつかめる」→「どう解けばいいか考えられる」→「結果として勉強が楽しくなる」という良いサイクルが生まれます。逆に、どんなに暗記が得意でも、問題文を読み違えれば正しい答えにはたどりつけません。
読む力は、学びのスタート地点。読解力が身についている子ほど、「わかった!」という経験を積み重ねながら、自信を持って勉強に向かえるようになります。
自分の気持ちや考えを言葉で伝えられるようになる
読解力が育つと、「読む力」だけでなく「伝える力」も伸びていきます。
本や文章を通して「人の考え方」や「気持ちの表現」に触れることで、「自分の思いをどう言葉にすれば伝わるか」を自然と学んでいけるのです。
例えば、友達と意見が違ったときに「そういう考え方もあるんだね」「私はこう思うよ」と伝えられるのは、相手の言葉を理解し、自分の意見を整理できる力があるから。この“相手を理解して、自分の考えを伝える力”は、まさに読解力から生まれるものです。
また、小さいうちは親子の会話の中でもその変化を感じられます。以前は「うまく言えなくて泣いていた」「何となくイヤ」としか言えなかった子が、「〇〇だから悲しかった」「△△してほしかった」と、少しずつ自分の気持ちを具体的に伝えられるようになります。
気持ちを言葉で表せるようになると、誤解やトラブルも減り、人との関係もぐっとスムーズに。「読む力」は、「伝える力」へとつながり、学校生活や友達関係、そして将来のコミュニケーションにも確実に生きていきます。
本や文章を楽しむ力がつき、学びの幅が広がる
読解力が育ってくると、読むこと自体がだんだん楽しくなってきます。物語の世界に入り込んで登場人物の気持ちを想像したり、説明文から「へぇ、そうなんだ!」と新しい発見をしたり——そんな“知る喜び”を味わえるようになるのです。
「前は本を読んでもよく分からなかったけど、今はおもしろいと思えるようになった」
そんな変化が見えてくると、子どもの表情もぐんと明るくなります。読む力がつくことで、自信や意欲も育っていくからです。
さらに、読解力がつくと、学びの世界も一気に広がります。
図鑑で動物の生態を調べたり、料理のレシピを自分で読んで作ったり、ニュース記事から社会の出来事に関心を持ったり——「読める力」は、新しい知識や体験への入り口になります。
読解力は、“学ぶ力”そのもの。
本や文章を楽しむ力がつけば、学びはもっと面白く、世界はもっと広く感じられるようになります。「読むことが好き」という気持ちは、子どもの一生の財産になるのです。
“読める力”は、子どもの未来を大きく育てる力
読解力は、すべての学びやコミュニケーションの土台です。
文章を「読む」「考える」「まとめる」経験を積み重ねることで、子どもは自分の考えを整理し、相手の気持ちを理解できるようになります。
その力は、国語だけでなく算数・理科・社会、さらには人とのかかわり方や日常生活にも生きていく力です。
家庭でできる読解力アップのコツは、むずかしい勉強ではありません。「一緒に本を読む」「感想を話す」「言葉の意味を調べてみる」——そんな小さな関わりの積み重ねが、確かな力になります。
「読むことが好き」「知ることが楽しい」と感じられる時間を、親子で一緒に増やしていきましょう。読解力は、未来への扉を開く“生きる力”へとつながっていきます。
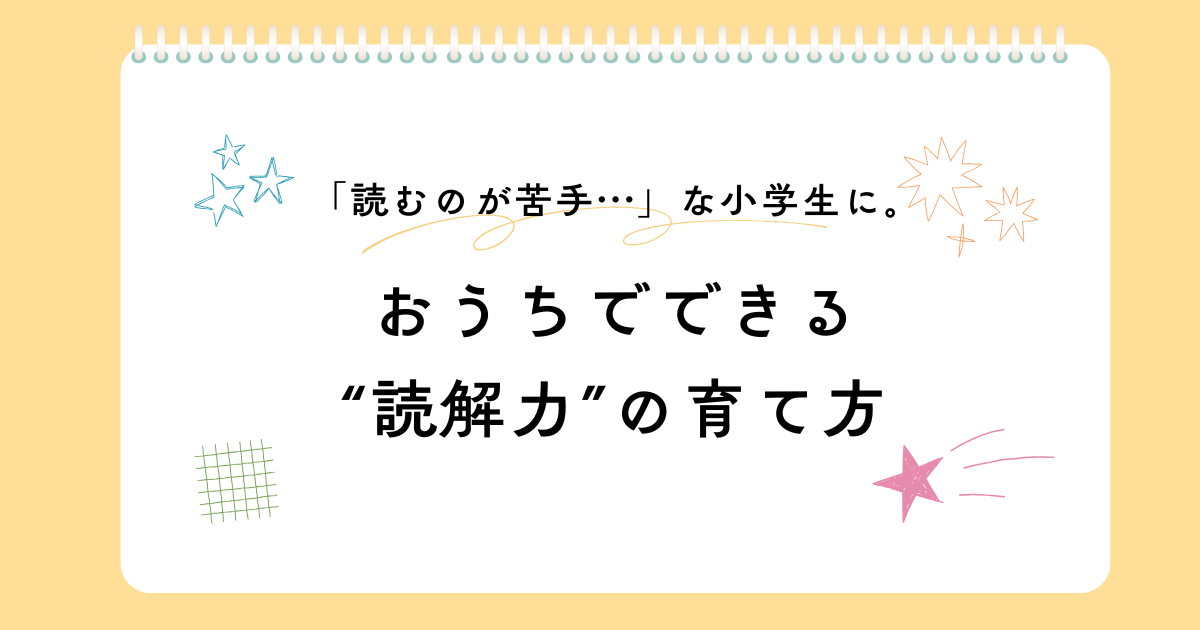

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=19347828&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8294%2F9784095018294_1_5.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=21155324&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7501%2F9784095017501_1_7.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント