「3歳になったのに、まだ言葉がはっきりしない…」
「“さ行”がうまく言えないけど大丈夫かな?」
そんなふうに、お子さんの発音について心配になることってありますよね。
実は、私自身も今まさに3歳の次女について、「周りの子はもっとはっきり話しているのに、うちの子は少し発音が不明瞭かも…」と感じることがあります。
でも、発音の発達には大きな個人差があり、3歳ではまだうまく言えない音があるのはとても自然なことなんです。
この記事では、3歳頃のことばの発達の目安や、実際に我が家でも実践している家庭でできることばのサポート法などについて詳しくご紹介していきます。あわせて、相談や受診を考えた方が良いケースについてもわかりやすくまとめています。
「大丈夫だよ」という安心と、「こんな風に見守ればいいんだ」というヒントをお届けできれば嬉しいです。
3歳児のことばの発達の目安
3歳頃は、「ことばの世界」がぐんと広がる時期です。
昨日までうまく言えなかった言葉が、ある日突然スラスラ出てきたりして、その成長に親の方が驚かされることも。
しかし一方で、「同じ年齢なのに、うちの子はまだあまりしゃべらない…」と不安になるママやパパも多いことでしょう。
ここでは、3歳児のことばの発達の目安について詳しくご紹介します。
3歳で一般的にできるようになる会話・発音
3歳頃になると、赤ちゃん言葉から少しずつ“会話らしい会話”ができるようになります。
- 2語・3語をつなげて話す
→例:「ママ、いっしょにあそぼ」「これ、〇〇ちゃんの!」
- 簡単な質問に答える
→例:「今日は何をしたの?」→「こうえんへいった」
- 自分の気持ちを言葉で伝える
→例:「いやだ」「おいしい」「たのしい」
まだ発音が不明瞭で聞き取りにくいことも多いですが、「ことばで伝えよう」とする姿勢が見えてくるのは大きな成長のサインです。
指差しで伝えていたお子さんも、少しずつ言葉で伝えようとするようになってきます。
たとえ聞き取りづらかったとしても、ママやパパが「そうなんだね」と受け止めてあげることで、会話はどんどん広がっていきますよ。
よく見られる3歳児の発音の特徴
3歳児の発音は、まだまだ未完成で当然です。大人が聞くと「ちょっと違うな」と思うこともよくあります。
- 「さ行」が「た行」になる
→例:「さかな」→「たかな」
- 「ら行」が言いにくい
→例:「りんご」→「いんご」
- 複雑な言葉を省略する
→例:「いただきます」→「いたたちゅ」
こうした言い間違いは、多くの3歳児に共通して見られるものです。
ほとんどの場合は成長とともに自然に整っていくので、「うちの子だけ言えないのかも…」と焦らなくても大丈夫。
実際に、うちの長男も「アンパンマン」を“パンマン”、長女は“アンパン”と呼んでいました。こういう言い間違いは他にもたくさんありましたが、いつの間にか正しい発音で話すようになっていました。
今では「小さいころは、こんな風に言っていたよね」と笑いながら振り返る、かわいい思い出になっています。
発音の間違いは今しかない成長の一コマ。楽しむ気持ちで聞きながら、「そうだね、〇〇だね」とさりげなく正しい言葉を返してあげるのがポイントです。
「さ行」が言えないのはいつまで様子を見ていい?
「いす」が「いちゅ」、「さかな」が「たかな」——。
こんなふうに、3歳前後のお子さんが「さ行」を「た行」に置き換えて発音することはよくあります。
「かわいいなあ」と思う反面、親としては「いつから正しく発音できるようになるんだろう…」と心配になることもありますよね。
ここでは、「さ行」を正しく言えないのはいつまで様子を見ていいのかについて、詳しくご紹介します。
3歳で「さ行」が言えないのは自然なことが多い
3歳頃のお子さんによく見られるのが「さ行」の発音の難しさです。
舌先を上の歯の裏にあてて息を出す「さ行」の発音は、大人には簡単に思えても、小さな子どもにとってはのとても高度な動きです。
そのため、他の音に比べて習得がゆっくりで、3歳の段階でまだ正確に発音できないのは自然なことです。
「まだ言えないから遅れているのでは?」と焦る必要はありません。この時期は、温かく見守ってあげることが大切です。
就学前に発音できるようになる子が多い
4~5歳頃になると舌や口の動きが発達し、少しずつ正しい発音ができるようになってきます。
多くの子どもは就学前の5~6歳頃までにははっきり「さ行」が言えるようになると言われています。
「同じ年齢の子はちゃんと言えているのに、うちの子はまだ言えない…」と不安になるかもしれませんが、ことばの発達には大きな個人差があります。
「ゆっくりだけど少しずつ上手になっている」という視点で見守っていけると安心です。
様子を見ていくポイント
次のようなポイントを見ながら様子を見てくと安心です。
- 3歳半~4歳頃:少しずつ「さ」に近い発音が出てくる
- 5歳頃:多くの子が自然に正しく発音できるようになってくる
- 6歳以降:ほとんどの子が「さ行」を習得
「まだ言えない=遅れている」と考える必要はありません。
むしろ「一生懸命伝えようとしている姿」を受け止めて、「そうだね、〇〇だね」とやさしく言い直して返すことが、お子さんにとって大きな励みとなります。
もし、6歳以降も「さ行」が発音できない場合は、一度専門機関に相談してみると安心です。
発音がはっきりしない原因とは?
3歳前後で「言葉は出ているけど、はっきり聞き取れない」というのはよくあることです。発音が不明瞭に聞こえる背景には、いくつかの原因が考えられます。
①発達途中の口まわりの機能
舌や唇、あごの動きは、成長とともに少しずつ器用になっていきます。
特に、「さ行」や「ら行」の音は舌の動きが複雑で難しいため、3歳頃ではまだうまくコントロールできない子も多いのです。
②言葉の経験や語彙の少なさ
まだ話し始めて間もない子は、まず「伝えること」や「単語を覚えること」に集中しているため、発音まで意識が回らないことがあります。
遊びや会話を通して語彙が増えてくると、自然と発音もはっきりできるようになっていきます。
③聞き取りやすさや発達の個人差
子どもの声は高く小さいため、発音できていても大人には聞き取りにくいことがあります。
また、ことばの発達には大きな個人差があるため、発音がはっきりしないからといって、必ずしも問題とは限りません。成長の中で自然に整っていくケースも多くあります。
④耳の不調による影響
まれに中耳炎などの耳の不調があると、正しく音を聞き取りにくくなり、発音にも影響が出ることがあります。
「聞き返しが多い」「聞こえに不安がある」と感じる時は、耳鼻科に相談してみると安心です。
家庭でできることばのサポート法
発音がはっきりしない時期でも、家庭でのちょっとした工夫が「ことばの発達」を助けてくれます。
大切なのは「練習させること」ではなく、日常生活の中で自然にことばに触れる機会を増やしてあげること。
ここでは、我が家でも実際に取り入れているサポート法をご紹介します。
①楽しく「まねっこ遊び」で発音を促す
歌や手遊び、擬音語などを取り入れて「まねっこ遊び」を楽しみましょう。
「このクッキー、サクサクだね」「すずがリンリン鳴ってるよ、リンリンリン♪」など、日常会話に擬音語をたくさん散りばめるだけで、子どもは自然に真似して声を出したくなります。
また、童謡や手遊び歌には「さしすせそ」「らりるれろ」などの音が自然に含まれているので、発音の練習にぴったりです。
- いっぽんばしこちょこちょ
- むすんでひらいて
- やきいもグーチーパー
- ひげじいさん
- てをたたきましょう
- 大きなくりの木の下で
お子さんのお気に入りの曲があれば、CDや動画を流して一緒に歌うのも◎
遊びながら声を出すことで、無理なく発音が身についていきます。
②絵本・読み聞かせで音のリズムに触れる
絵本は、正しい発音や言葉のリズムに出会える最高の教材です。
とくに、擬音語や繰り返しの表現が多い絵本は、子どもが真似して発音しやすいく、発音の練習にもなります。
- 「はみがきれっしゃ しゅっぱつしんこう!」(くぼまちこ作)
- 「おめんです」(いしかわこうじ作)
- 「パンダ銭湯」(tupera tupera作)
- 「しろくまのパンツ」(tupera tupera作)
お気に入りの絵本を繰り返し読むのも良いですし、いろいろな絵本に触れることで語彙や表現もどんどん広がっていきます。
③正しく直さず「やさしく返す」声かけ
子どもが「たかな(=さかな)」と言ったとき、ママやパパは「そうだね、さかなだね」と自然に返してあげましょう。
「違うよ、“さかな”って言うんだよ」と強く直す必要はありません。
正しい発音をやさしく返してあげるだけで、子どもは少しずつ自分で音をつかめるようになっていきます。
受診や相談を考えた方がいいケース
3歳前後の子どもは、まだ発音が不明瞭でも自然なことが多く、成長とともに少しずつ改善していくケースがほとんどです。
しかし、次のような様子が見られる場合には、一度、小児科や耳鼻科、言語聴覚士などの専門機関に相談してみると安心です。
- 3歳半を過ぎても2語文(「ママきて」など)が出ない
- 5歳を過ぎても「さ行」「ら行」など多くの音がはっきりしない
- 特定の音だけでなく、全体的に言葉が聞き取りにくい
- 言葉数が極端に少ない
- 会話の中でよく聞き返しがあり、耳の聞こえに不安がある
- 発達全般に遅れがあるように感じる
こうしたサインがあるからといって、必ずしも大きな問題があるとは限りません。
「気になるけれど、相談したら大事になってしまいそうで…」と不安に思い、様子を見続けてしまうご家庭も少なくありません。
でも、「相談=問題」ではありません。少しでも気になることがあるなら、専門家に診てもらうことで、
- 「成長の範囲内なんだ」
- 「少し練習をした方がいいのか」
といったことが分かり、ママやパパの安心にもつながります。
発音の不安は「成長のプロセス」として温かく見守りましょう
3歳で発音がはっきりしないのは、発達の途中にある自然な姿です。特に「さ行」や「ら行」は難しく、正しく発音できるようになるのは5~6歳頃ということも少なくありません。
とはいえ、親としては「うちの子大丈夫かな…?」と心配になる気持ちはよく分かります。
実際にわが家の3歳の次女も二歳半健診で言葉数や発音について保健師さんに指摘を受け、不安になった経験があります。
でも、上の子どもたちの成長を見てきた中で感じるのは、「ことばの発達には個人差が大きい」ということ。だからこそ、親である私自身が焦らず、心配しすぎず、家庭でできる「ことばにふれる時間」を大切にしています。
もし不安が続いたり、「ちょっと気になるな」と思うことがある場合には、専門家に相談するのも安心につながる一歩です。「相談する=問題がある」ではなく、「子どもの発達を一緒に見守ってもらうためのサポート」だと考えてみてください。
ことばの成長は親子で楽しめるプロセスです。焦らず、一歩ずつ歩んでいきましょう。
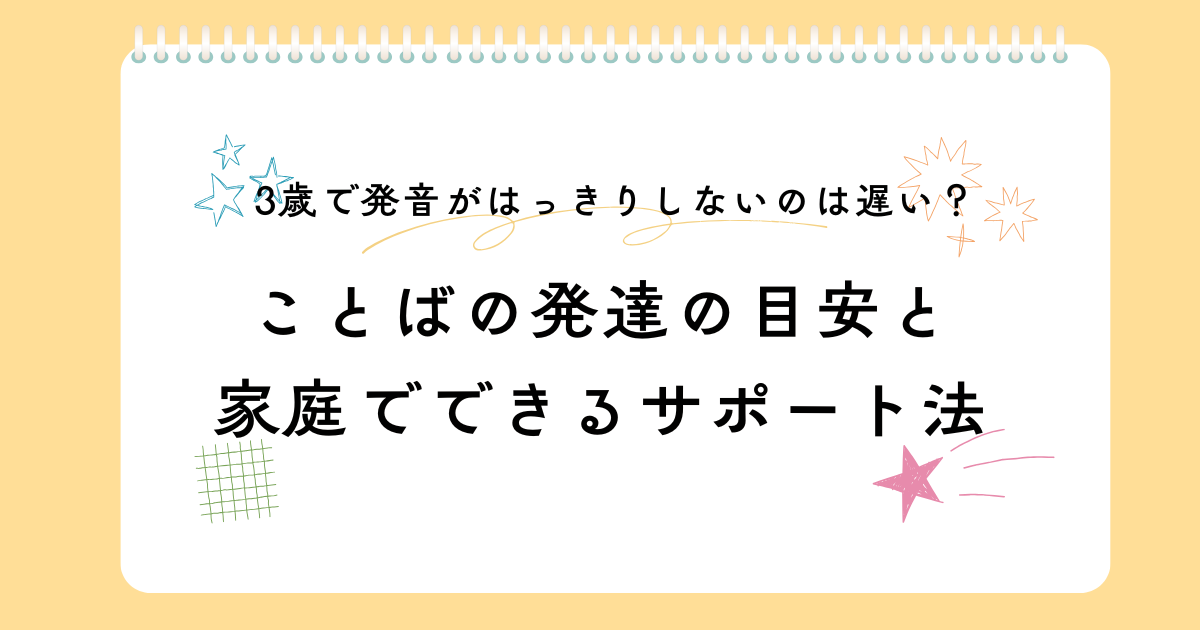
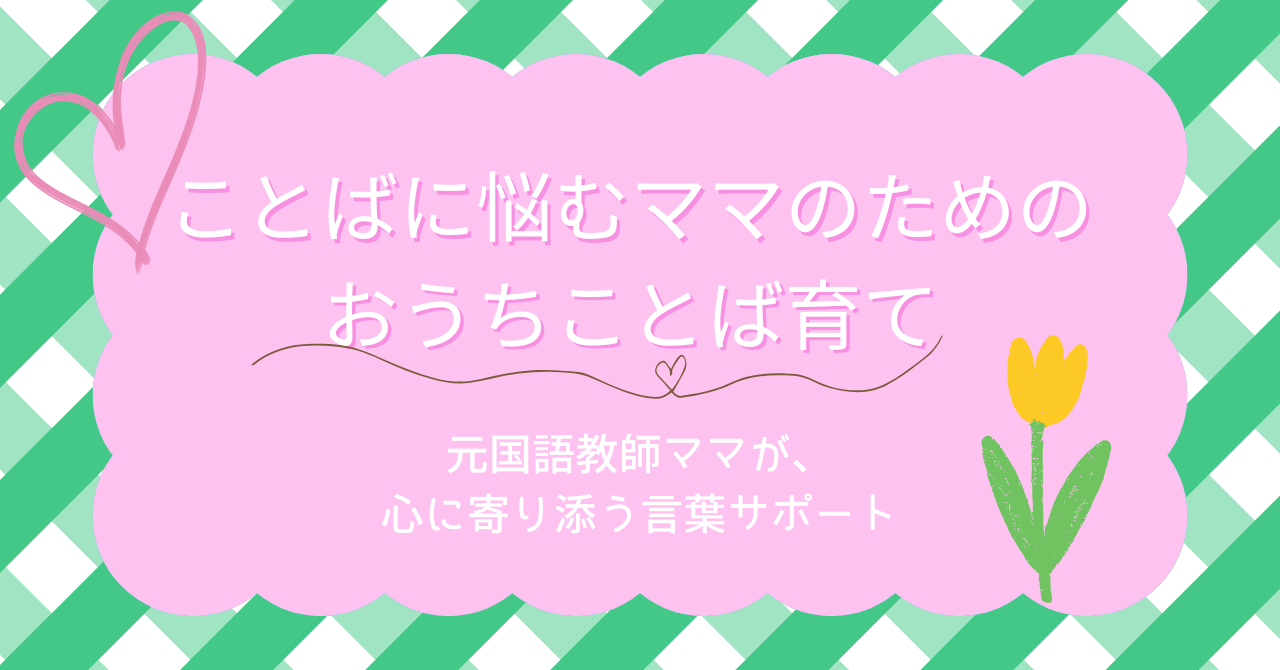
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=17276798&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6893%2F9784752006893.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=16423505&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1103%2F9784031271103.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=16572678&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0861%2F9784871100861_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=15953432&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5473%2F9784893095473_1_7.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
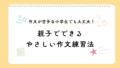

コメント