夏休みの宿題といえば、自由研究やドリルと並んで悩みのタネとなるのが「読書感想文」。毎年の定番ではあるものの、「どう書いたらいいの?」「読書感想文を書かせるのが大変…」と頭を抱える保護者の方も多いのではないでしょうか。
でも、実はちょっとした準備と親の声かけ次第で、子どもは自分の言葉で感想文を書けるようになるんです。
そこで、この記事では、小学生向けに読書感想文の書き方と子どもが書きやすくなる声かけのコツをご紹介します。また、感想文の基本構成や、書きやすくなる本選びのポイントについても簡単にお伝えします。
元国語教師としての経験をもとに、「読書感想文、意外と書けるかも!」と感じてもらえるようにわかりやすく丁寧にまとめました。夏休みの宿題に不安を感じている方のヒントになれば嬉しいです♪
読書感想文が苦手な子が多いのはなぜ?
「読書感想文が一番苦手…」「何を書いたらいいの?」
夏休みになると、こんな声があちこちから聞こえてきます。
実際に私が国語教師として働いていた時も「読書感想文が一番イヤ!」という子どもが本当にたくさんいました。書き始めるまでに時間がかかってしまったり、白紙のまま手が止まってしまったり…。読書感想文に苦手意識を持つ子は多くいます。
なぜ、こんなにも読書感想文に苦手意識を感じる子が多いのか、その主な理由は大きく分けて3つあります。
そもそも「感想文って何?」が分かっていない
そもそも「感想文」がどんなものなのかが分かっていない子がとても多いんです。
読書感想文には「正解」がないため、何を書いていいのか分からなくなってしまうんですよね。本を読んだものの、最初の一文が書けずに手が止まる…。そんなお子さんの姿、見たことある方も多いのではないでしょうか?
焦ってどうにか書き始めても、「あらすじ」ばかりになってしまって、肝心の“感想”が書けていない、というケースはとてもよくあるパターンです。
自分の考えを言葉にするのが難しい
読書感想文は、「本を読んで、自分がどう感じたか、どう考えたか」を書くもの。つまり、自分の思いを“言葉にして表現する力”が必要になります。
でも、実はこの「自分の気持ちを言葉にする」のが苦手な子がとても多いんです。
これは読書感想文に限らず、国語全体に関わること。作文や意見文が苦手な子も、根本には同じような課題を抱えていることが多いです。
実は「本選び」が原因になっていることも!
意外と見落としがちですが、「どんな本を選ぶか」も感想文が書けるかどうかに大きく関わってきます。
難しすぎたり、興味の持てない本を選んでしまうと、そもそも内容が頭に入らなかったり、「何となく読んだだけ」で終わってしまったりすることも…。
その結果、「何も感じなかった」「感想が思い浮かばない…」となってしまうんですよね。
私がこれまで見てきた中でも、感想が1行だけ、あとは全部あらすじ…という感想文は珍しくありませんでした。それは読み方や書き方のコツがつかめていないから。
でも大丈夫!少しだけ準備をして、保護者の方がちょっとした声かけをしてあげるだけで、感想文はぐんと書きやすくなりますよ。
本選びについて詳しくご紹介していますので、気になる方はこちらの記事もチェックしてみてくださいね。
▶【関連記事】【元国語教師ママが解説】読書感想文に悩む親子へ|本の選び方と学年別おすすめ本
読書感想文を書く前にやるべき準備とは?
読書感想文が苦手な子にとって、「さあ、書いてみよう!」といきなり言われても、なかなか書き出せないもの。
でも、読書感想文を書き始める前に“ちょっとした準備”をしておくだけで、子どもにとって書きやすさがぐんと変わるんです。
ここでは、スムーズに書き始めるためにやっておきたい2つのポイントをご紹介します。
「どんな本を選ぶか」がカギ!
読書感想文が書けるかどうかは、「本選び」でほとんど決まると言ってもいいほど大切です。
「課題図書の中から適当に選べば大丈夫でしょ」と思って選んだ本が、子どもにとって興味のない内容だった場合、読んでも心も動かされず、なかなか感想も浮かんできません。
ついつい親の方が焦って「これでいいんじゃない?」と本選びをしてしまいがちですが、できればお子さんと一緒に「どれにする?」と話しながら選んでみてください。自分で選んだ本なら、子どもも読みやすく、感情移入もしやすくなります。
※読書感想文の本の選び方やおすすめの本については、別記事で詳しくご紹介します!
本を読む前に「ひと声」かけておくと◎
実は、本を読む前のちょっとした声かけが、読書感想文の書きやすさを大きく左右するんです。
例えば…
- 「どんなところが心に残ったか、あとで教えてね」
- 「もし自分がこの登場人物だったらどうする?を想像しながら読んでみてね」
- 「好きなセリフがあったらあとで教えてね」
こんなふうに、少しだけ“感想を意識して読む”ような声かけをしておくだけで、読み終わったあとに自分の考えが出てきやすくなります。
また、中学年〜高学年のお子さんなら、付箋を活用して「気になった場面」や「心が動いたところ」に印をつけておくのもおすすめ!さらに、その理由も一言メモしておけば、いざ読書感想文を書くときにとても役立ちます。
読む前に“ちょっとした視点”を持つだけで、読書感想文はぐんと書きやすくなりますよ。
読書感想文の構成を知ろう!~基本の流れ~
読書感想文を書くとき、まず知っておきたいのが「文章の流れ(構成)」です。
何となく書き始めると、「あらすじだけになっちゃった…」「話があちこちに飛んでまとまらない…」なんてことになってしまうことも。
でも、大丈夫!読書感想文には基本の“型”があります。この“型”を知っておけば、スムーズに書き進められて、読みやすい文章になります。
ここでは、読書感想文の基本構成について詳しくご紹介します。
①導入:本を選んだ理由や読む前の気持ち
まずは、「なぜこの本を読もうと思ったのか」から書き始めましょう。
たとえば…
- タイトルが気になった
- 表紙の絵に惹かれた
- 学校や家族にすすめられた
- 昔から〇〇に興味があった など
また、「読む前はどんな気持ちだったか」も一緒に書くと、その後の感想とつながって自然な流れになります。
②あらすじ:ポイントをしぼって簡潔に!
「読書感想文にあらすじは書いちゃダメ?」とよく聞かれますが、実は短く入れるのはOKなんです。
ただし、長々と物語を説明するのはNG。読書感想文を読んだ人が「この感想文だけで本を読んだ気になっちゃった…」となるのは避けたいところ。
大切なのは、「自分の感想につながる部分」にしぼって、必要な背景を簡潔に伝えることです。
たとえば…
「この本は、〇〇が△△に挑戦する物語です。ある日〇〇が~~して…」
というように、感想を書くために必要な場面だけをサラッと紹介するイメージでOK!
※読んでいない人にも何となく話が伝わる程度で十分!
「この本、ちょっと読んでみたいかも」と思わせられたら大成功◎
③感想の中心:心に残った場面と自分の気持ち
ここが読書感想文で一番大切なところ!
自分の心が動いた場面や、印象に残ったことを中心に書いていきます。
たとえば…
- どんな場面が心に残ったか
- 登場人物のどんな気持ちや行動に共感したか
- 自分だったらどう思うか、どう行動したいか
など、自分の気持ちと本の内容を結びつけて書くと、しっかりした感想になります。
また、「どうしてそう思ったか」という理由も一緒あわせて書くのがポイント。「悲しかった」「おもしろかった」だけで終わらせずに、「なぜ悲しかったのか」「どこがどうおもろかったのか」を書いてみましょう。
④まとめ:本を読んで気づいたことや考えたこと
最後は、本を読んだ後の自分の気持ちや考えたことをまとめて締めくくります。
例えば…
- 〇〇くんの頑張りを見て、私もあきらめずにチャレンジしたいと思いました。
- この本を読んで、家族や友達の大切さに改めて気づいたので、もっとたくさん話をしていきたいと思いました。
など、本の内容と自分の生活や気持ちをつなげると、読書感想文がグッと深まります。
【5ステップ】読書感想文の書き方
ここからは、実際に読書感想文を書くための5つのステップをご紹介します。
「何から書けばいいの?」「どうやって進めたらいいか分からない…」と迷っているお子さんも、このステップ通りに進めれば大丈夫!
順を追って取り組むことで、スムーズに書き進められて、自然と読みやすい感想文になりますよ。
ステップ①:思い出そう!本を読んで心に残ったところ
まずは、本を読んで「心に残った場面」や「気になった登場人物」「いいな、すごいなと思った部分」などを思い出してみましょう。
たとえば…
- どんな場面が印象的だった?
- どのセリフが心に残った?
- 登場人物の行動「すごいな」と思ったところは?
- そのとき、あなたはどう感じた?
こういったことを、メモ用紙や付箋にどんどん書き出しておくと、あとでとても役に立ちます。
文章にしようとせず、箇条書きでOK!この段階では、思い出したことをどんどんメモしておきましょう。
ステップ②:構成を決めよう!自分の感想につながる順番で
次に、読書感想文の流れ(構成)をざっくり決めてみましょう。
ここで文章の構成を整理しておくと、書く時に迷わず進められます。
先ほど紹介した4つの基本構成を思い出してみましょう。
- 本を選んだ理由
- あらすじ(感想につながる部分だけ)
- 心に残った場面と自分の気持ち
- 本を読んで気づいたこと・考えたこと
それぞれについて、簡単にメモを取っておくと書きやすくなります。
ステップ③:書き出しは簡単に!導入からスタート
準備が整ったら、いよいよ文章を書き始めます。
最初の部分は、「本を選んだきっかけ」や「本を読む前の気持ち」などを書いてみてください。
たとえば…
- 「この本を読もうと思ったのは、タイトルが気になったからです。」
- 「姉に勧められて読み始めました。」
- 「読む前は、どんなお話なのかな?とワクワクしていました」
最初にスッと書き始めることができると、続きも書きやすくなりますよ。
ステップ④:心に残った場面と自分の気持ちを書く
読書感想文の一番大切なのが、この「感想」の部分です。
印象に残った場面について、「どう感じたか」「なぜそう思ったのか」をしっかりと書きましょう。
たとえば…
主人公の〇〇が、あきらめずに努力する姿に感動しました。
私もピアノの練習がうまくいかず、くじけそうになったことがあるので、〇〇の頑張っている姿に勇気をもらいました。
大切なのは、「自分の経験や気持ち」と結びつけること。本を読んで感じたことを自分の生活とリンクさせることで、説得力のある読書感想文になります。
ステップ⑤:「この本を読んで気づいたこと」でしめくくろう
最後は、「この本を読んでどう思ったか」「これからどうしたいか」などをまとめて、読書感想文をしめくくりましょう。
たとえば…
- 「〇〇くんの行動を見て、私も困っている人がいたら優しく手を差し伸べられる人になりたいと思いました。」
- 「私も、苦手なことがあっても最後まであきらめずにチャレンジしたいと思いました。」
ポイントは、ステップ④で書いた内容と同じことを繰り返さないこと。感想のまとめとして、自分の考えや変化を簡潔に書くようにしましょう。
うまく書けないときはどうする?“親の声かけ”のコツ
読書感想文の構成や書き方が分かっていても、いざ書こうとすると手が止まってしまう…という子は少なくありません。
そんなときにこそ、ママやパパの“ちょっとした声かけ”が、子どもにとって大きな助けになります。
ここでは、子どもが前向きに読書感想文に取り組めるようになる声かけのコツをご紹介します
声かけは「一緒に考えるスタンス」で
「どうだった?」とざっくりとした質問をしてしまうと、「ふつう」「おもしろかった」「わからない」など、あいまいな返事で終わってしまうことも…。
そんなときは、質問の仕方をちょっと工夫してみましょう。
たとえば…
- 「どの場面が一番心に残った?」
- 「主人公の〇〇がこんなことしてたけど、どう思った?」
- 「もし自分だったら、どうすると思う?」
子どもと一緒に考えるようなスタンスで声かけをしてあげると、子どもは自分の気持ちや考えを少しずつ言葉にしやすくなります。
感想文は「自分の気持ちを言葉にする練習」でもあるので、そばで見守りながら考えるきっかけを作ってあげてくださいね。
書けたら「すごいね!」としっかりほめる
感想文に“正解”はありません。だからこそ、書けた内容を評価するのではなく、「書けたことそのもの」をたくさんほめてあげるのが大切です。
つい、「もっとこう書いたほうがいいんじゃない?」「それってあらすじじゃない?」などと言いたくなってしまう気持ち、とってもよく分かります。
でも、ママやパパがダメ出しをしてしまうと、「せっかく頑張って書こうとしていたのに…」と子どものやる気がしぼんでしまうことも。
最初は、箇条書きや口頭で思ったことを話すだけでもOK!
「一文でも書けたら、それだけですごいこと!」
「うまく言えなくても大丈夫」「自由に書いていいんだよ」と安心させてあげて、少しずつ書けるようになっていければそれで十分です。
どうしても進まないときは「もう一回読んでみよう」もアリ!
どうしても手が止まってしまうときは、無理に書かせようとせずに、思い切ってもう一度読み直してみるのも一つの方法です。
- 「気になったところだけもう一回読んでみようか」
- 「さっきの場面、ちょっと読み返してみようか」
そう声をかけてあげると、改めて感じたことや新しい発見が生まれることもあります。
【学年別】サポートのちょっとしたコツ
読書感想文は、学年によってサポートの仕方を少し変えると、子どもがグッと書きやすくなります。
たとえば、低学年なら「一緒に話しながら考える」、中学年なら「なぜそう思ったの?」と理由を引き出す声かけ、高学年なら「自分の意見を深める質問」を意識するのがポイントです。
それぞれの学年に合わせたサポートのコツを、別の記事で詳しく紹介していきますので、よかったらあわせてご覧ください。
▶【関連記事】【保存版】読書感想文のテンプレート集|小学1~6年生対応&すぐ書けるワークシート付き
感想文が書きやすくなる!おすすめの本3選
実は、「どんな本を選ぶか」で読書感想文の書きやすさは大きく変わってきます。
物語に感情移入ができると、自然と「おもしろかった」「心に残った」といった感想が生まれ、自分の言葉で書きやすくなります。
ここでは小学生に人気があり、心が動きやすい内容で、感想も書きやすいおすすめの本を3冊ご紹介します。
①『ともだちや』(内田麟太郎/偕成社)
「1時間100円で友達になってあげる」という主人公のキツネのユニークなアイデアから始まるお話。
読み進めるうちに、「本当の友達って何?」「友情はお金で買える?」と、子ども自身が考えるきっかけになる絵本です。
感想文におすすめの理由:
- 低学年でも読みやすい短めの文章と親しみやすい絵
- 登場人物の行動に「自分だったらどうする?」と想像がしやすい
- 「ともだち」について自分の体験と重ねて考えやすい
②『ふわふわとちくちく』(斎藤孝/日本図書センター)
身近な言葉の使い方を通して、言葉の選び方や思いやりの大切さを教えてくれる一冊。
子ども自身の体験と重ねて、「今自分が使っている言葉は相手を傷つけていないか?」「これからはどんな言葉を使っていきたいか」を自然に考えられる内容です。
感想文におすすめの理由:
- 日常生活で感じたことと結びつけやすく、感想が書きやすい
- 言葉の力や、人とのかかわりについて自分の考えが深まりやすい
- 「これから自分はどうしたいか」が自然と書けて、読書感想文のまとめにもつなげやすい
③『チョコレート戦争』(大石真/理論社)
高級洋菓子店のショーウインドウを割ったと決めつけられた子どもたちが、大人たちに立ち向かうユーモアと正義の物語。
「本当に正しいことって何だろう?」「大人の言うことはいつも正しいのかな?」と問いかけながら読める一冊です。
感想文におすすめの理由:
- 「正しさ」「勇気」「仲間」といった考えやすいテーマ
- 自分の学校生活や人間関係と結びつけて感想が書きやすい
- 高学年でも読み応えがあり、物語としても面白い
どんな本が感想文に向いているか迷ったときは?
「うちの子に合いそうな本がわからない…」「他にもおすすめは?」という方は、別記事で【学年別のおすすめ本】をご紹介しています。ぜひ、そちらも参考にしてみてくださいね。
“書きやすい本”と“ちょっとした工夫”で感想文は変わる!
夏休みの宿題の定番、読書感想文。
「何を書いたらいいのかわからない…」「全然進まない…」そんなお子さんの様子に毎年ちょっぴりため息が出てしまう方も多いのではないでしょうか。
でも実は、本の選び方や、読むときの声かけなど、ほんのちょっとした工夫で、ぐんと書きやすくなることもあるんです。
ついつい「こう書いたら?」「それじゃダメでしょ」と言いたくなる気持ち、すごくよくわかります。
でも、読書感想文には正解がありません。一番大切なのは、子どもが自分の言葉で素直な気持ちを書くことです。
たとえうまく書けなくても、「そう思ったんだね」と受け止めてもらえるだけで、子どもは安心して自分の気持ちを出せるようになります。
まずは、「一緒に考えてみようか?」そんな一言から始めてみて下さい。そして、一文でも書けたら「やったね!」「すごいね!」と、思いっきり褒めてあげましょう!
褒められるって子どもにとってはすごく大きな励みになります。
実は私自身、国語の教師を目指すきっかけになったのが読書感想文で褒めてもらえたことでした。
中学生のときに感想文で賞をもらい、担任の先生から「とても良かったよ。文章書くの上手だね」と言ってもらえたことが、今でも心に残っています。
それまで「自分は文章を書くのが得意だ」なんて思ったことは一度もなかったけれど、その経験が自信になって「書くことって楽しいかも」と思えるようになりました。
一人でも多くの子どもたちに、そんなふうに「書くって楽しい!」と感じられる体験をしてほしい。そして、そのきっかけを作ってあげれるのは、日々そばで成長を見守っているパパやママです。
今年の夏が、そんな“気づき”や“成長”を味わえる時間になりますように。親子で、ゆっくり楽しみながら進んでいってくださいね♪
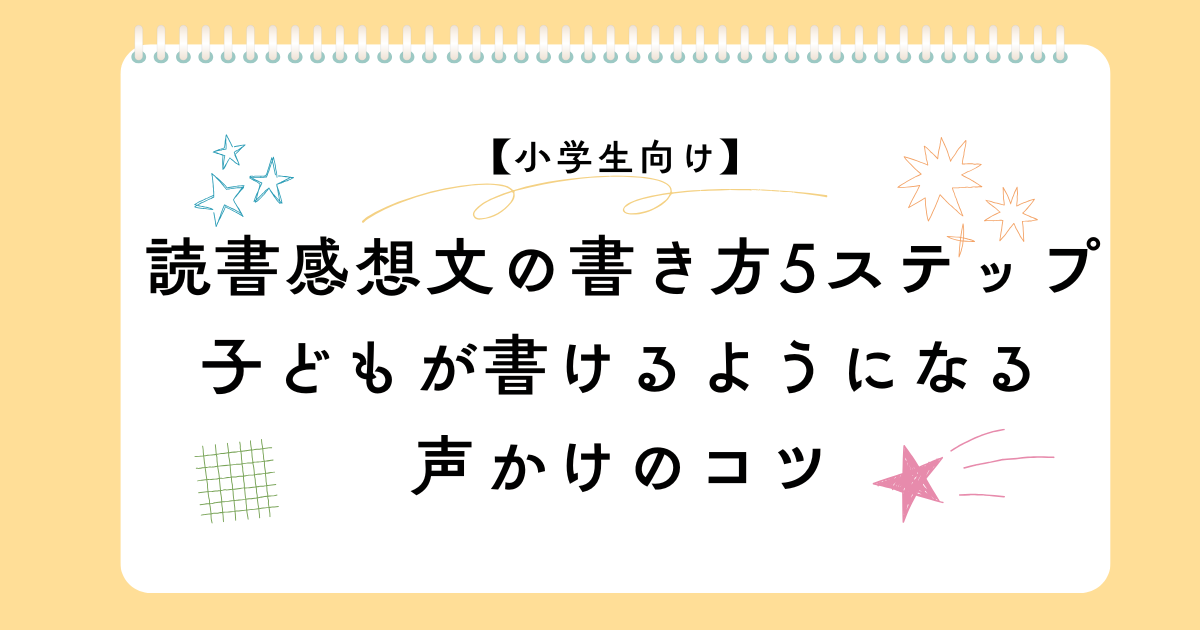
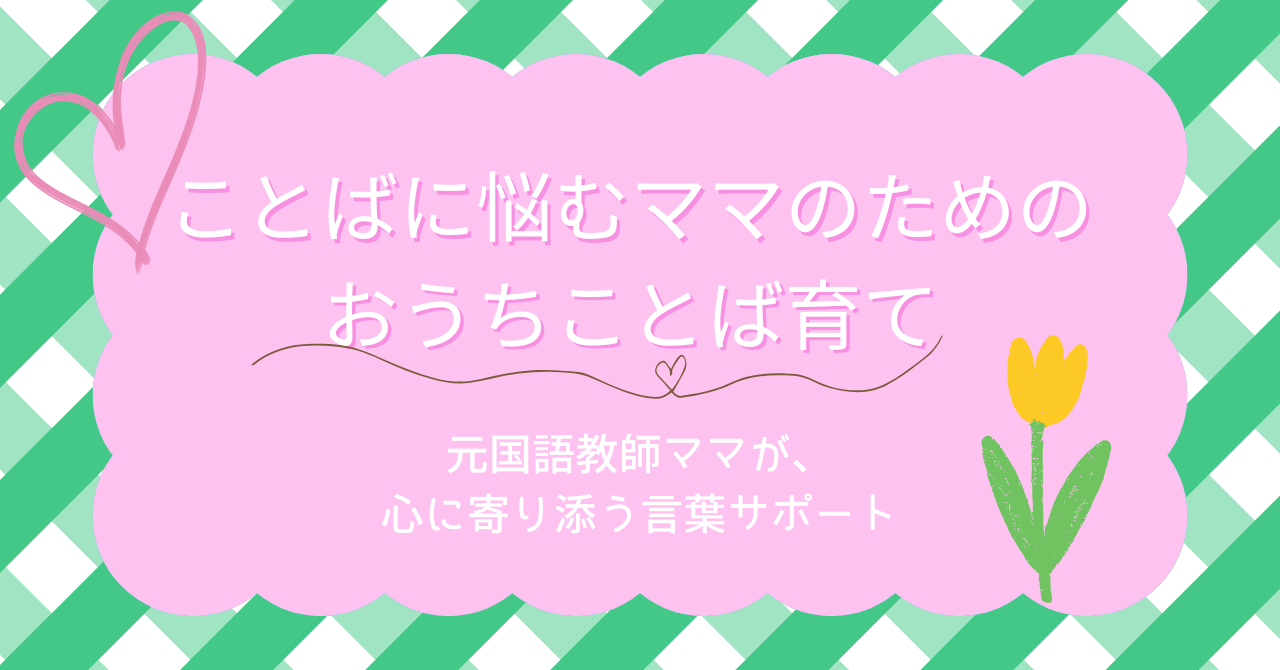


コメント