「国語のテストの点数がなかなか取れない」「読書感想文が思うように進まない」——。
そんな姿を見て、「うちの子は国語が苦手なのかも…」と心配になるママやパパも多いのではないでしょうか?
算数や理科と違って、国語は“勉強の仕方”がイメージしにくい科目。さらに“書く問題”には単純な〇×でつけれる答えがなく、「なんとなく合ってるかな」と適当に答え合わせをしてしまうこともありますよね。
国語の力は、決して生まれつきのセンスだけで決まるものではありません。家庭でのちょっとした工夫や習慣づけで、少しずつ「読む」「書く」「考える」力を伸ばしていくことができるのです。
この記事では、国語が苦手な子に共通する特徴や家庭でできる克服ステップ、具体的な勉強法を元国語教師ママの視点から詳しくご紹介します。どれも今日からすぐに実践できる内容ばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
国語が苦手な子に共通する特徴
国語が苦手だと感じる小学生には、いくつか共通する特徴が見られます。
ここでは代表的な4つの特徴をご紹介します。
本や文章を読むのが苦手
「文字を読むこと」自体に苦手意識を持つ子は意外と多いものです。
好きなマンガなら読めるのに、長い文章や興味のない文章になると眠くなってしまったり、音読でつまずいたりすることがあります。
読むことに抵抗感があると、問題文を理解する前に疲れてしまい、正しい答えにたどり着きにくくなります。
語彙(ことば)の数が少ない
国語で特に大切なのは、「言葉の意味を正しく理解しているかどうか」です。
「なんとなくわかる」で済ませてしまう子は多いですが、テストでは“あえて間違いやすい部分”が出題されるため、語彙力の不足は大きなつまずきにつながります。
例えば、「状況」「理由」「感情」といった抽象的な言葉の意味がつかみにくいと、文章全体を正しく理解するのが難しくなってしまいます。
話の要点をつかむのが苦手
文章を読んでも「結局何が書いてあったの?」と要点をまとめるのが苦手な子もいます。
国語では「筆者が一番伝えたいことは何か」「この文章の内容に合うものはどれか」といった問題がよく出題されます。
細かい部分に気をとられてしまい、大切なポイントを見失ってしまうと、こうした問題に答えるのは難しくなります。
自分の考えや感想を言葉にするのが難しい
感想文や作文になると「何を書けばいいのかわからない」と手が止まってしまう子も少なくありません。
自分の気持ちを言葉で表現する経験が少ないと、書くことに自信をなくしてしまいます。
「自由に書いていいって言われても…」「感想って言われても“おもしろかった”しかない…」と戸惑ってしまう子を、私自身もたくさん見てきました。
家庭でできる克服ステップ
ここでは、国語に苦手意識を持っている子でも、おうちで取り入れられる克服ステップをご紹介します。
日常生活の中で無理なく続けられる工夫ばかりなので、気軽に試してみてくださいね。
①読書習慣を“楽しい時間”に変える
国語力の土台となるのは、やはり「読むこと」。
でも、読むことに苦手意識を持っている子に「本を読みなさい」と言っても逆効果になることも…。
そこでおすすめなのが、「親子で一緒に読む」こと。声に出して交代で読んだり、絵本の読み聞かせをするのも効果的です。また、最初は絵本や図鑑、マンガなど、子どもが好きなジャンルから入ると読書への抵抗感が減ります。
まずは、「読書=楽しい時間」と思えるような環境づくりを意識しましょう。
②日常に語彙力を増やす工夫を
語彙力は一気に伸ばせるものではなく、毎日の小さな積み重ねで育ちます。
例えば、「ことばカード」で遊んだり、「しりとり」で新しい言葉を取り入れるのもおすすめです。普段の会話の中でも「これどういう意味だと思う?」と自然に問いかけるだけで、子どもの考える力が鍛えられます。
遊び感覚で取り入れることで、子ども自身が「言葉を知るって楽しい!」と感じられるポイントです。
③「要点をつかむ」力を生活の中で育てる
文章を理解するためには、「大事なところを見抜く力」が欠かせません。この力は、国語の問題集だけでなく、家庭でのちょっとした会話でも育てることができます。
例えば、テレビやアニメを見たあとに「今日のお話はどんな内容だった?」「一番面白かったとろこはどこ?」と聞いてみましょう。さらに、「どうしてそう思ったの?」と理由をたずねると、自然に要約力や考える力が育っていきます。
④書くことを“ハードルの低い形”から始める
作文となると「何を書けばいいのかわからない」と手が止まってしまう子は少なくありません。その場合、いきなり長文を書くのではなく、短く気軽に書けるものから始めましょう。
例えば、「今日楽しかったことを一言書く」「好きなキャラクターを紹介する」など、たった一文でOKです。慣れてきたら少しずつ文を増やしていくと、自然に文章を書くことへの抵抗感が薄れていきます。
家庭でできる具体的な勉強法
ここからは、日常生活に取り入れやすい具体的な勉強方法をご紹介します。国語が苦手な子でも取り組みやすい工夫ばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。
①文章読解のトレーニング法
文章を正しく理解して答える力は、国語の基礎です。いきなり長文に挑戦すると苦手意識が強まってしまうので、まずは短い文章から始めましょう。
短い文章を読んで質問に答える練習
「この物語の主人公はだれ?」
「どこでの出来事?」
など、一問一答形式のやさしい質問を繰り返しましょう。この練習を繰り返すと、読み取る力が自然とついていきます。
絵本や教科書の短文を題材にしてもOK!
マルチステップで“読む→理解→答える”を意識する
「文を声に出して読む→内容を自分の言葉で説明する→答える」という3段階を意識させると、読解の流れが身に付きます。
慣れてきたら「筆者が一番伝えたいことは何?」といった要約問題にも挑戦すると効果的です。
- 読んだあとに「どんな話だった?」と質問して、内容を簡単に説明してもらう
- 感情をこめて読む練習をする
実はこれは私が学生の時にしていた勉強法。とにかく「本読み」をして、書いている内容を把握することを意識して勉強していました。
こうした工夫で「ただ読む」から「理解しながら読む」へとつながっていきます。
②書く力を伸ばすトレーニング法
作文が苦手な子は「書く」ことに大きなハードルを感じています。そこで、最初はとにかく短く、気軽に書ける取り組みから始めるのがポイントです。
ひとこと作文・絵日記から始める
「今日楽しかったこと」「好きな食べ物」など、一文でいいので書く習慣をつけると徐々に書けるようになっていきます。絵を描いてからひとこと添える「絵日記」形式もおすすめです。
「書き出しの型」を使う
作文の練習をするときは、「書き出しの型」を使って練習しましょう。
1.「〇〇をして楽しかったです。」
2.「なぜなら、△△だからです。」
書き出しの型があるだけで、子どもは迷わず書き始められます。
型にあてはめて書くことに慣れてきたら、少しずつ自分の表現に広げていけるようになります。
感想文は“会話形式”でサポート
「どこが面白かった?」「どんな気持ちになった?」と親が質問し、答えをそのまま書かせると、感想文も自然に形になります。
③語彙力・漢字の効率的な増やし方
語彙力や漢字力は国語力のベース。ドリルで詰め込むよりも、生活の中で楽しく触れるほうが身に付きやすいです。
しりとり・カルタなど遊びを通して語彙を増やす
ことば遊びは「楽しみながら語彙が増える」一石二鳥の方法です。特にカルタは耳と目から同時に覚えられるので効果的。
新しい言葉に出会ったときにすぐ意味を確認
分からなかった言葉や新しく出てきた言葉をノートに書き、意味や例文も一緒に調べてまとめていきます。
親子で「この言葉、どんなときに使えるかな?」と会話をすると記憶に残りやすくなります。
この方法は、現在小学2年生の息子もしている勉強法。辞書は「ドラえもん」の辞書を使用しています。最初は乗り気ではなかった息子も、ドラえもんの辞書なので抵抗なく辞書引きしてくれています。
低学年のうちはこれで、高学年になると語彙の数も増えてくるので、こちらの辞書に変えていくことがおすすめです。
「今日のことば」を決めて使ってみる
語彙ノートから、例えば、「発見」という言葉を選んで、「今日の発見は何?」と会話に取り入れると自然に定着します。
④親子で楽しく取り組む工夫
勉強は「苦しいもの」ではなく、「一緒に楽しめるもの」と感じさせることが継続のカギです。
タイマーを使って「5分だけ!」で集中
「今から5分だけ国語タイム」と区切ると、子どもも負担を感じにくくなります。
短時間でも毎日の積み重ねが効果的です。
ドリルの購入すると、アプリを取得すれば、アプリと連動して学習できるドリルがあります。
こちらは実際に小2の息子が使用しているドリルです。
アプリにタイマー機能もついているので、「このページを〇分で終わらせた!」と喜んでいます。アプリで連動しているので、遊び感覚かつ集中して取り組めているのでとてもおすすめです。
スタンプカードやご褒美シールを活用
取り組んだ日にはシールを貼るだけでも達成感につながります。
お気に入りのスケジュール帳を購入し、学習した日にシールを貼るのもおすすめです。
また、ポケモン好きのお子さんには、ポケモンドリルがおすすめ!各ページを終わらせるとポケモンシールが張れる台紙つきなので、ポケモンを集める感覚で勉強に取り組んでくれますよ。
親も一緒に取り組む
親が横で本を読んだり、一緒に日記を書いたりする姿を見せることで、子どもは自然と「ひとりじゃない」「勉強は特別なことじゃない」と感じられるようになります。
ときにはゲーム感覚で挑戦したり、学校とは少し違う方法で「ママ(パパ)と一緒に勉強するのが楽しい!」と思えるような時間を作ってあげましょう。
「できた!」を積み重ねて、国語の力と自信を育てよう
国語の学びで大切なのは、正解を求めることよりも「自分の言葉で表現する楽しさ」を感じることです。読むこと・書くことを“勉強”としてではなく、“楽しみ”として親子で共有できると、自然と国語力が伸びていきます。
最初から完璧を目指す必要はありません。小さな「できた!」の積み重ねが、お子さんの自信と学ぶ意欲につながります。無理なく、楽しく続けることを大切に、親子で国語の世界を広げていきましょう。
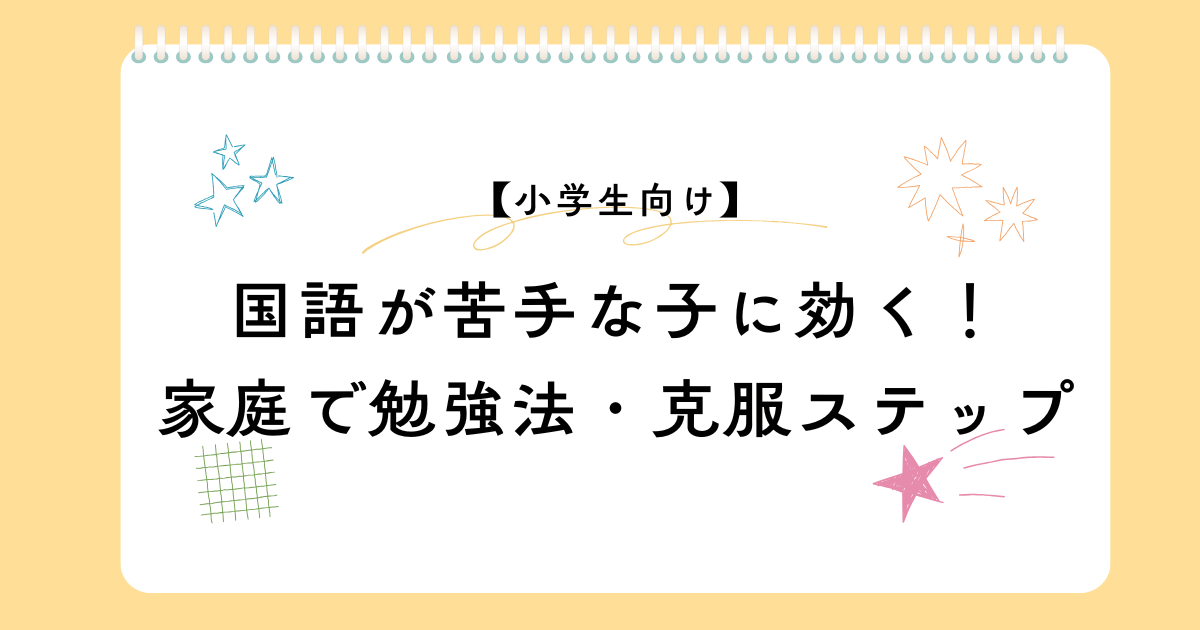

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=19347828&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8294%2F9784095018294_1_5.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=21155324&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7501%2F9784095017501_1_7.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=19893661&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0540%2F9784053050540.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=20873344&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6517%2F9784092536517.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
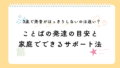
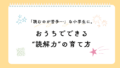
コメント