「読書感想文の本、どれにしたらいいんだろう…」
書き方も気になるけど、そもそも“どんな本を読めばいいのか分からない”というママやパパは多いのではないでしょうか。
課題図書を選んだ方がいいのかな?
それとも、子どもが好きな本でいいのかな?
実は、この“本選び”がうまくいくと、読書感想文がぐっと書きやすくなります。つまり、読書感想文の出来は、「本選び」でほとんど決まるといっても過言ではありません。
私も国語教師として学校でたくさんの子どもたちの読書感想文を見てきましたが、「本が合っていないから感想が浮かばない」というケースは本当に多くありました。普段は文章を書くのが得意な子でも、本の選び方が合っていないと、思ったことが書けずに苦戦してしまうことがあるんです。
でも逆に、子どもの気持ちに寄り添った一冊に出会えたら、感想文が苦手な子でも自然に言葉が出てきます。
そこでこの記事では、読書感想文の選び方のポイントと学年別おすすめ本を詳しくご紹介します。
お子さんにぴったりの本を見つけて、読書感想文を「苦手な宿題」から「ちょっと自信が持てる経験」に変えていきましょう!
読書感想文の本選びで大切にしたい3つのポイント
「うちの子、本を読むのがあまり得意じゃなくて…」
こんな声をよく耳にします。実際、本を読むのが苦手な子は「字が少ないもの」「絵が多い本」「好きなアニメのノベライズ」などを選びがちです。もちろん“読書のきっかけ”としては大切なことですが、感想文となると「どう書いていいかわからない…」となってしまうケースが多いのです。
だからこそ、本を読むのが苦手なお子さんほど、一人で選ばせるのではなく、親子で一緒に選ぶことがおすすめです。
ここでは、読書感想文の本選びで特に大切にしてほしい3つのポイントをご紹介します。このポイントを意識するだけで、読書感想文はぐっと書きやすくなりますよ。
子どもが「興味を持てるテーマ」から選ぶ
読書感想文でいちばん大切なのは、子どもが「読んでみたい!」と思える本を選ぶことです。
大人が「感動するし、いい本だよ」とすすめても、お子さん自身が興味を持てなければ、読み進めるのも一苦労…。
おすすめは、いくつかテーマを絞って選んだ本を掲示し、「この中から読んでみたいと思う本はある?」とお子さんに選ばせてあげる方法です。
子どもの“好き”に寄り添ったテーマや、自分と似た主人公の物語を選ぶことで、自然と感想も湧きやすくなります。
「心が動く場面」がある本を選ぶ
読書感想文は、物語のあらすじをまとめるものではありません。大切なのは、「心が動いた瞬間」をどう表現できるかです。
登場人物の気持ちに共感したとき、出来事を自分に置き換えて考えたとき…。そうした気づきや感情を引き出してくれる本こそ、感想文に適しています。
感動する場面だけでなく、笑える場面やドキドキする展開も立派な「心が動いた瞬間」です。
「どんな気持ちになれる本か」を意識して選ぶと、書きやすさが変わってきます。
学年に合った“読みやすさ”を意識する
いくら内容が素晴らしい本でも、文章が難しすぎると感想文は書けません。
学年に合わせて“ちょうどよい読みやすさ”を意識しましょう。
- 低学年:絵が多くて短めの物語や、わかりやすい表現の本
- 中学年:冒険や友情など、少し長めでも夢中になれる本
- 高学年:心の成長や社会的テーマに触れられる本
このように、学年に合った読みやすさを意識して選ぶと、読書も感想文もスムーズに進みます。
課題図書と自由図書、どちらを選んだらいい?
読書感想文の本を選ぶとき、多くのママやパパが迷うのが「課題図書にするべき?それとも自由図書でいいの?」という点ですよね。
「本選びが面倒だから、とりあえず課題図書から適当に選んでおこう…」なんていう声もよく聞きます。
でも、実はその“何となく選んだ一冊”が、子どもにとっては読みにくくて感想が出てこない原因になり、読書感想文がますます苦手に感じてしまうこともあるんです。
そこで、ここでは、課題図書と自由図書のメリット・デメリットを整理していきます。どちらを選ぶと良いかの参考にしてみてくださいね。
課題図書を選ぶメリット・デメリット
課題図書には、安心感がある反面、注意したいポイントもあります。
学校で推奨されている課題図書は、学年に合った本が多く、「ちょうどいいレベルの本」を選びやすいのがメリットです。
ただし、内容に共感できるかどうかは子ども次第。興味が持てないと「ただ読むだけ」で終わってしまい、感想が浮かばない…というケースも少なくありません。
自由図書を選ぶメリット・デメリット
自由図書には「自分らしさを出せる」メリットがあります。
自由図書は、自分の“好き”や“興味”を生かせるのが大きな魅力です。
ただし、選んだ本が難しすぎて「最後まで読めない」「内容を理解できない」ということもあるので注意が必要です。
どちらを選ぶのが正解?
結論は…「どちらを選んでも正解」です。
一番大切なのは、課題図書か自由図書かではなく、「お子さんが感想を書きやすい本かどうか」です。
- 読書に慣れている子→自由図書で、自分の好きなテーマを選ぶとやる気アップ
- 読書が得意ではない子→課題図書から、学年に合った読みやすい本を選ぶと安心
迷ったときは、まずは課題図書をチェックして、その中に子どもの興味に合うものがあればそれを選ぶ。もし「どれもピンとこないな」と感じたら、自由図書に目を向けて探してみる。
そんな流れで進めると失敗が少なくなりますよ。
【学年別】読書感想文におすすめの本リスト
本の選び方は分かったけれど、たくさんある本の中から結局どんな本を選んだらいいかわからない…
そんなママやパパへ、ここからは低学年・中学年・高学年それぞれにおすすめの本をご紹介します。
小学校低学年(1~2年生)向けおすすめ本
『おこだでませんように』(くすのきしげのり作)
いつも怒られてばかりの男の子が、「ぼくのことを分かってほしい」と願う姿を描いたお話。子どもたちが共感しやすく、「自分だったらどうするかな?」と感情を重ねやすい一冊です。
『おしいれのぼうけん』(ふるたたるひ・たばたせいいち作)
おしいれに閉じ込められた子どもたちの冒険を描いた物語。ハラハラする展開に子どもたちが夢中になりやすく、感想も書きやすいです。
『ともだちや』(内田麟太郎作)
お金で「ともだち」を売るキツネの物語。友情とはなにか?本当のともだちとは?と、子どもが自分の経験と重ねて考えやすいテーマです。
小学校中学年におすすめの本
『わすれられないおくりもの』(スーザン・バーレイ作)
大切な存在との別れを通して、「思い出」や「受け継がれるもの」をテーマにした絵本。感情移入がしやすく、心の成長を感じられる内容です。
『てんこうせいのおはなしやさん』(北川チハル作)
転校生との出会いを通じて、友情や人とのつながりを考えられる物語。学校生活に近い内容で、子ども自身も感想を書きやすいです。
『エルマーのぼうけん』(ルース・スタイル・ガネット作)
勇気あるエルマーが、どうぶつ島でりゅうの子を助けるために冒険するお話。工夫や勇気、優しさに触れられるので、子どもが感想を書きやすいです。
小学校高学年におすすめの本
『世界がもし100人の村だったら』(池田香代子・再話)
世界を100人の村に置き換えて、格差や文化の違いを身近に感じられる一冊。「自分がその村の一員だったらどうする?」と考えながら感想を書きやすい本です。
『君たちはどう生きるか』(吉野源三郎作)
正義や友情、悩みを通して「どう生きるか」を考える本。子どもが自分の考えを感想文にまとめやすい一冊です。
『ガラスのうさぎ』(高木敏子作)
戦争で家族や大切なものを失う体験を描いた作品。重いテーマですが、「平和」や「命」について考えながら感想が書きやすい一冊です。
読書感想文を書く時のコツ
読書感想文を書く時は、「心が動いたこと」を中心に書くのがコツです。
登場人物や自分の体験と比べながら、感じたことを順番に整理すると書きやすくなります。
読書感想文の詳しい書き方やステップはこちらの記事でご紹介していますので、ぜひあわせてチェックしてみてください。
本選び次第で読書感想文はぐっと書きやすくなる
読書感想文は、実は「どの本を選ぶか」で書きやすさが大きく変わってきます。
子どもが興味を持てるテーマや、心が動く場面がある本、学年に合った読みやすさを意識して選ぶと、自然と感想も出やすくなります。
そして何より大切なのは、お子さんが「読みたい!」と思える本を選ぶこと。
今回ご紹介した学年別おすすめ本リストも参考にしながら、親子で一緒にぴったりの一冊を見つけてみてくださいね。
今年の読書感想文が、「苦手な宿題」ではなく、「楽しく書けた!」という自信につながる経験になりますように。
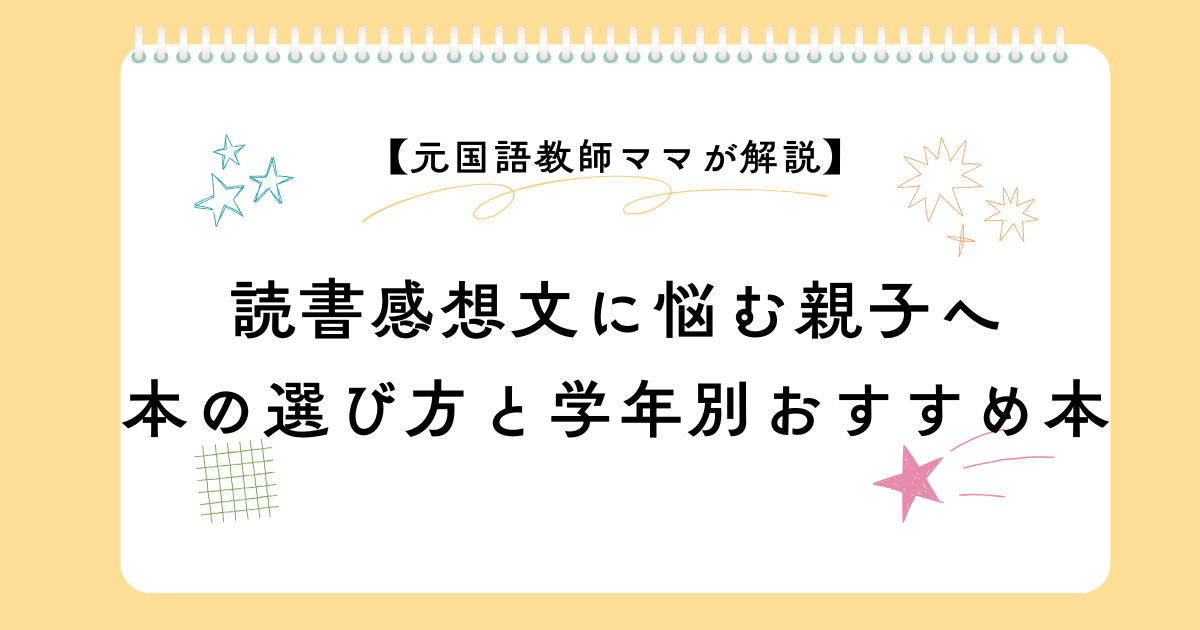
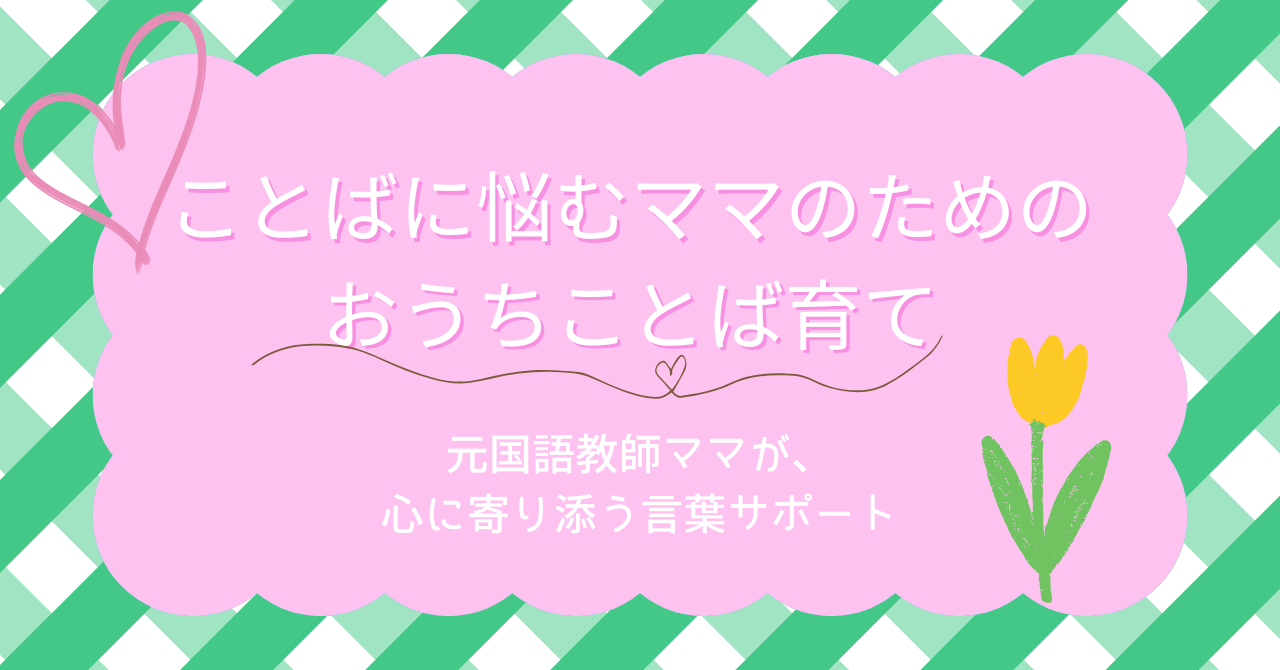


コメント