「読書感想文、何を書かせたらいいの?」
夏休みの定番宿題に、毎年頭を抱えてしまう…そんなご家庭も多いのではないでしょうか?
子どもは「どう書いたらいいのかわからない…」、親は「どう教えたらいいのか分からない…」そんな風に戸惑ってしまうこと、ありますよね。
そこでこの記事では、小学1年生〜6年生まで、学年別に使える「読書感想文のテンプレート」と「感想文が書きやすくなるワークシート」をご用意しました。
学年に合わせた書き方のコツやちょっとしたサポートを取り入れるだけで、子どもたちは驚くほどスムーズに読書感想文を書き進めることができます。
「今年の夏は、読書感想文がちょっと得意になったかも!」
そんな体験ができるよう、親子で一緒に進められるヒントをたっぷりお届けしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね♪
感想文を書く前に|基本の型と書き方をチェックしよう
感想文を書く前に、まず知っておきたいのが「基本の型(構成)」と「書き方の流れ」です。これを知っているだけで、「どんなふうに書き進めたらいいか分からない…」という悩みがぐんと減り、自然と感想がまとまっていきます。
読書感想文の基本の型や書き方のステップについては、以下の記事でわかりやすく解説しています。「はじめの一文が書けない…」「あらすじってどこまで書けばいいの?」と悩んでいる方にもおすすめの内容なので、まだ読んでいない方は、まずはこちらをチェックしてみてくださいね!
▶【関連記事】【小学生向け】読書感想文の書き方5ステップ|子どもが書けるようになる声かけのコツ
【学年別】読書感想文のテンプレート&ワークシート
「基本の型」や「書き方のステップ」は理解したけれど、実際にどんなことを書いたらいいのか分からない…
そんなお悩みをお持ちの方へ、小学1年生~6年生までの各学年に合わせた、「読書感想文のテンプレート(書き出し例や構成案)」と「感想文が書きやすくなるワークシート(思いついたことを書き込める簡易フォーマット)」をご用意しました!
小学1・2年生向け|親子で一緒に話しながら考える!読書感想文テンプレート&ワークシート
小学校低学年のお子さんは、まだ本を読んだり、文字を書いたりすることに精一杯で、なかなか読みながら感想を考えるのは難しい時期です。
また、自分の考えをうまく言葉にできないことも多いので、会話を通して感想を引き出してあげることが大切です。「どんなお話だった?」「どこが一番心に残った?」など、具体的に、やさしく一緒に振り返るような質問を投げかけてあげましょう。
小学校低学年用ワークシート
ワークシートを使った読書感想文テンプレート例
わたしは、(① この本をおかあさんにすすめられてよみました。)
この本のなかで、いちばんこころにのこったところは、(② キツネが1じかん100えんおかねをもらってともだちになるところです。「ともだちや」としておかねをもらってともだちになるなんて、それはともだちといえるのかな?とおもいました。でもさいごはオオカミのおかげで、キツネが「ほんとうのともだち」のことがわかって、わたしもうれしくなりました。)
この本をよんで、(③ ほんとうのともだちって、じぶんのいちばんたいせつにしているたからものもあげれるくらいたいせつにおもえるひとのことなんだとおもいました。だから、わたしもおかねじゃなくて、やさしさでともだちとなかよくなれるといいなとおもいました。そして、これからもともだちをたいせつにしたいとおもいます。)
小学3・4年生向け|「なぜそう思ったの?」と理由を引き出す読書感想文テンプレート&ワークシート
小学校中学年になると、物語の内容をしっかり理解できるようになり、「あらすじ+自分の感想」を文章にまとめられる力がついてきます。
ここで大事になるのが、「どうしてそう思ったのか?」という“理由”をしっかり書くこと。「どうしてそう思ったの?」「自分だったらどうする?」と“理由”や“自分との違い”を引き出す質問をしましょう。
自分の考えに理由を加えるだけで、ぐっと読み応えのある感想文になりますよ。
小学校中学年用ワークシート
ワークシートを使った読書感想文テンプレート例
私がこの本を選んだ理由は、(① タイトルに「ふわふわ」と「ちくちく」という言葉が入っていて、なんだか気になったからです。)
この本は、【簡単なあらすじを】。
このお話の中で心に残ったのは、(② 「「ふわふわことば」と「ちくちくことば」は、どんどんふえていくんだよ。」というセリフです。)わたしはこの部分を読んで、本当にその通りだと思いました。なぜなら、(③ 「ちくちくことば」のような人をイヤな気持ちにさせる言葉を使っている人は、その人も周りの人に「ちくちくことば」を言われると私も思うからです。)
この本を読んで、私は(④ 話す前に、「これを言ったら相手がイヤな気持ちにならないかな?」と考えるようにしたいと思いました。みんなが人を攻撃したりイヤな気持ちにさせたりするような言葉を使わず、人の気持ちを考えて話せるようになれば、人を傷つけたりしない優しい社会になると思います。私はそんな社会になるように、率先してふわふわことばを使っていきたいと思います。)
小学5・6年生向け|自分の考えを深める読書感想文テンプレート&ワークシート
小学校高学年になると、ただ感想を言うだけではなく、自分の価値観や考え方を掘り下げることが求められます。
「他の人はどう思うかな?」「主人公の〇〇はこのときどう考えていたと思う?」など視点を広げるような質問をしてあげましょう。
小学校高学年用ワークシート
ワークシートを使った読書感想文テンプレート例
私がこの本を読もうと思ったのは、(① 表紙とタイトルにひかれたことと、「戦争」という言葉が気になったからです。)
この物語は、【簡単なあらすじを】。
この物語の中で一番印象に残ったのは、(② ショーウインドウを割ったと疑われた子どもたちが、自分たちの正しさを信じて大人に立ち向かっていく場面です。)なぜなら、(③ 自分だったら大人に反論するのは勇気がいりそうで、怖いと感じたからです。でも、この物語の子どもたちは「自分たちの気持ち」を大切にして行動していて、すごいと思いました。)
この本を読んで、(④ 自分の意見をもつことや自分を信じることの大切さを学びました。)これからは、(⑤ 私も「正しい」と思ったことを勇気を持って言える人になりたいと思いました。)
こんなときは?つまづきやすいポイントと親のサポート法
読書感想文には正解がありません。だからこそ、「自由に書いていいよ」と言われると、かえって何を書けばいいのかわからず、難しく感じてしまう子も多いものです。
そこで、ここではよくあるつまずきポイントと、親としてできるサポートの工夫をご紹介します。
「何を書いたらいいかわからない…」と言われたら?
読書感想文が苦手な子にとって「感想を自由に書いたらいいんだよ」と言われても、何を書いたらいいのかわからないもの。
そのため、まずは、書く内容を整理するところから始めましょう。
「どんなお話だった?」「いちばんおもしろかったところはどこ?」など、ママやパパとの会話を通して一緒に振り返ることで、子どもは自分の感じたことに気づくきっかけになります。
親のサポートのポイント:
無理に答えを引き出そうとせず、「へぇ、そう思ったんだね!」と受け止めてあげる姿勢を大切に。
あらすじばかりになってしまう…
読書感想文が苦手な子が、つい「お話の内容を説明するだけの感想文になってしまった…」なんていうことはよくあること。
そんなときは、「このときどう思った?」「自分ならどうする?」と感情や考えに注目する質問をしてみてください。
親の声かけ例:
- 「主人公の〇〇くんが怒ってた場面、どうして怒っていたか分かる?」
- 「自分だったらあんなことをされたらどう思う?」
感想が「おもしろかった」だけで終わってしまう…
「おもしろかった」「かなしかった」など一言で終わってしまう場合は、理由を引き出す質問をしてみましょう。
「どこがおもしろかった?」「どうしてかなしかったの?」と少し質問をしてあげるだけで、子どもの中から感想のタネが出てきます。
子どもから出てきた言葉をつなげて文章にするのは、親のサポートが活きる場面です。
親の声かけ例:
- 「どの場面が一番おもしろかった?なんでおもしろかったの?」
- 「主人公の〇〇ちゃんと同じような経験をしたことある?」
言葉にするのが難しそうなときは?
気持ちはあるのに、それを言葉にするのが苦手な子もたくさんいます。そんな子にいくら「どう思ったの?」「それはなんで?」と繰り返し聞いても、言葉はなかなか出てこないものです。
そんなときは、お子さんが口に出して言ったことを、大人が代わりに書いて見せるのも一つの方法です。
たとえば…
子:「〇〇くん、ちょっとかわいそうだった」
親:「どうしてかわいそうだと思っの?」
子:「う~ん…なんか…かわいそう…」
親:「〇〇くんが寂しそうでかわいそうだと思ったのかな?」
子:「そう!!」
親:「じゃあ、“〇〇くんが寂しそうでかわいそうだと思いました”って書いてみようか」
親のサポートのポイント:
一緒に考えて、言葉のモデルを見せることが、次に自分で書くヒントになります。
サポートのしすぎに注意!
「こう書いたら?」「それはちょっと変だよ」など、ついつい大人の視点で口を出してしまいたくなることもありますよね…。
でも、大人が細かく指示しすぎると、子どもは「これで合っているのかな…」と不安になってしまいます。
大切なのは、「自分の言葉で書いた」という達成感を持たせてあげること。サポートは最小限にとどめ、子どもの気持ちや言葉を尊重してあげましょう。
親がかけたい言葉:
- 「あなたの気持ちが伝わってきたよ!」
- 「この言い方、あなたらしくていいね!」
また、どんな感想文でも、最後まで書けたことは大きな成果です。「すごいね!」「よく頑張ったね!」とたくさんほめて、成功体験として心に残してあげましょう。
本選びも重要!読書感想文が書きやすくなる本選びを
読書感想文の書きやすさは、本選びの時点で半分決まると言って過言ではありません。
あまりにも長くて難しい本や、テーマが抽象的すぎる本だと、読み終えるだけで疲れてしまい、感想を書く余力が残らないこともあります。
おすすめの本リストは、こちらの記事で紹介しています。
▶【関連リンク記事】【元国語教師ママが解説】読書感想文に悩む親子へ|本の選び方と学年別おすすめ本
今年の夏は、親子で楽しく読書感想文に挑戦しよう!
読書感想文は、「書く力」だけでなく、子どもの感じる力や考える力を育てる貴重な機会です。
ポイントは、最初から完璧を目指さず、「自分の言葉で書けた!」という達成感を大事にしてあげてくださいね。
今回ご紹介したテンプレートやワークシートを活用すれば、書き出しや構成に迷わず進められます。
親子で会話しながら、感想を少しずつふくらませていく過程も、きっと夏の良い思い出になりますよ。
「今年の読書感想文、今までよりも書けたかも!」という成功体験を、ぜひこの夏にさせてあげてみてください。
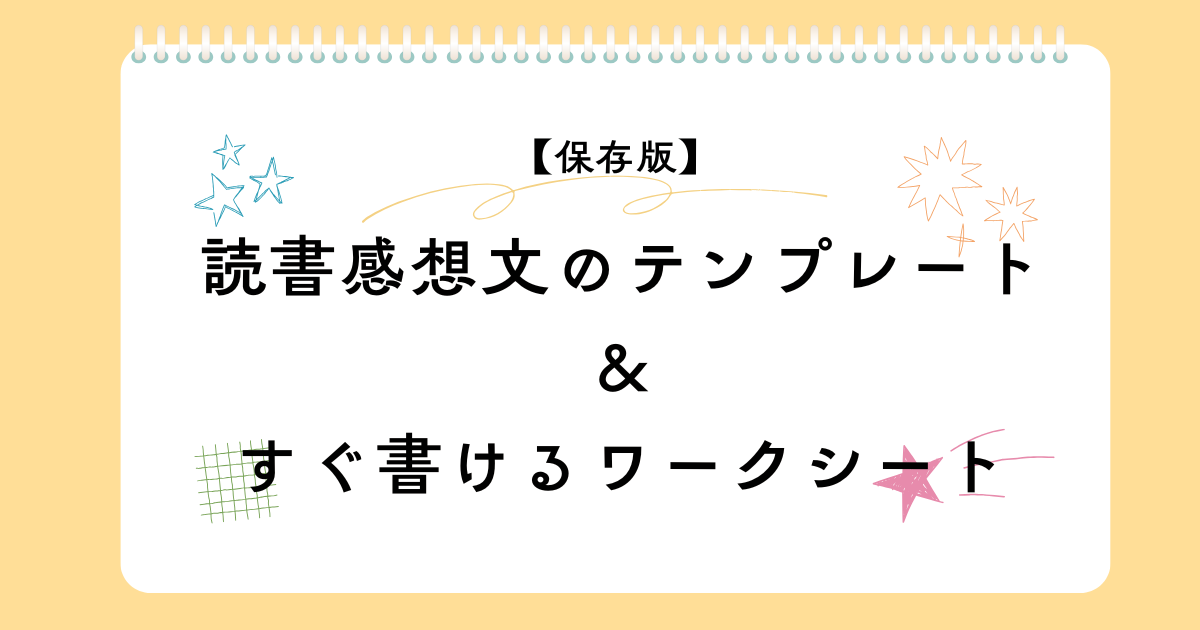



コメント