夏休みが終わり、2学期が始まると、少しずつ「高校入試」という言葉が現実味を帯びてきますよね。
「うちの子、国語が苦手みたいで…」
「国語だけなかなか点数が伸びなくて心配」
そんなふうに感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
国語は、数学や理科のように「これを覚えればすぐ点数アップ!」というわけにはいかない教科です。成果が目に見えにくい分、「本当に力がついているのかな?」と不安や焦りを抱きやすいのも当然のこと。
でも大丈夫。国語は、日々の積み重ねとちょっとした工夫で、着実に力を伸ばしていける教科です。そして2学期は、その学習を入試モードに切り替えるのにぴったりの時期でもあります。
そこで、この記事では、全国的な出題傾向をふまえながら、「高校入試の国語で差がつくポイント」と「家庭でできる勉強法」を詳しくご紹介していきます。
お子さんの将来を思って不安になる気持ちを少しでも和らげながら、「これならおうちでも取り入れられそう」と感じていただけるようなヒントをお届けできればと思います。
なぜ「2学期の国語学習」が高校入試で差をつけるカギなの?
2学期に入ると、学校や塾でも徐々に「入試を意識したモード」に切り替わっていきます。
それはなぜなのでしょうか?
2学期から入試シフトが始まる理由
2学期は、1年間の学習の中でもとくに重要な時期です。なぜなら、学校の授業内容や定期テストが、少しずつ高校入試のレベルに近づいていくからです。
実際、私が国語教師をしていたときも、2学期以降は「入試を意識した採点」や「出題傾向を反映した問題作成」に力を入れていました。ここで学習習慣を整えておくと、3学期や入試直前期にぐんと伸びやすくなるのです。
国語は暗記科目ではないので、一夜漬けでは成果が出にくい科目です。語彙を積み上げ、文章の読み方の型に慣れ、記述問題に取り組む—―そのすべてに時間と積み重ねが必要です。だからこそ、2学期からの学習スタートが大きな意味を持つのです。
夏休み明けは「苦手」が表面化しやすい時期
「夏休みに基礎を復習したはずなのに、2学期の授業が始まると点数が伸びない」
「思ったより文章が読めていない」
そんなふうに感じるお子さんは実は少なくありません。
国語力は一気に伸びるものではなく、日々の積み重ねの上に成り立つもの。語彙不足や読解への苦手意識は、学習内容が高度になる2学期に表面化しやすいのです。
でも、それはチャンスでもあります。弱点が見えてきた今だからこそ、対策の効果も出やすいのです。入試本番までにはまだ数か月あります。家庭での工夫次第で、大きく挽回することができますよ。
高校入試国語の出題傾向を知っておこう
国語の入試問題は、都道府県ごとに出題内容や形式に多少の違いがありますが、全国的に見ると共通する傾向があります。
まずはその「よく出るパターン」を知っておくことが大切です。出題傾向を意識して勉強することで、限られた時間で効率よく力をつけることができますよ。
出題傾向1:現代文(説明的文章・文学的文章)
どの地域でも必ず出題されるのが、長めの文章を読んで解く読解問題です。
- 説明的文章(評論・論説文など):筆者の主張や論理の展開を正しくつかむ力が求められます。
- 文学的文章(小説や随筆など):登場人物の心情や場面の状況を読み取る力が求められます。
また、単なる選択問題だけではなく、「本文中から抜き出す問題」や「記述問題」が多いのも特徴です。
出題傾向2:古文・漢文
ほとんどの入試で出題される分野です。長文ではなく、短めの文章で出題されることが多いです。
- 現代仮名遣いに直す
- 返り点を使って正しく読む
- 重要語句の意味を理解する
- 主語の把握する
- 大まかに内容を理解する
上記のように、基本をしっかり押さえておくことがポイントになります。
高校入試では、「詳しい文法の知識」よりも文章の大意をつかむ力が重視される傾向にあります。つまり、「基本の文法と語句」を押さえておけば得点しやすい、狙い目の分野でもあるのです。
出題傾向3:漢字・語彙・文法
漢字の読み書きや語彙の知識、文法問題もほとんどの地域で出題されます。
配点はそれほど大きくないものの、確実に得点できる落としたくない問題です。
普段から少しずつ積み重ねることで安定して点を取れるようになります。
出題傾向4:作文・要約・資料の読み取り
近年、特に重要性が増しているのが「自分の言葉で書く問題」です。
- 短い作文や意見記述
- 資料やグラフを読み取ってまとめる問題 など
ただ文章を読むだけでなく、条件を踏まえて自分の考えを整理し、わかりやすく表現する力が求められるのです。
字数指定や「原稿用紙の書き方に従う」などのルールもあるため、普段から条件付きで文章を書く練習をしておくと安心です。
高校入試国語で差がつく3つのポイント
国語は、得意な子と不得意な子の差が出やすい教科です。
実際に私が国語教師をしていたときにも、子どもたちからは
「国語なんて勉強しても意味がない」
「なんとなく解けるでしょ」
といった声をよく聞きました。
確かに、理科や社会のように「暗記すればすぐ点がとれる」教科ではありません。ですが、差がつくポイントを意識して取り組めば、着実に点数を伸ばすことができるんです。
差がつくポイント①:語彙力(言葉の知識)
文章を正しく理解するには、まず言葉の意味がわかることが大前提です。
同じ文章を読んでも「単語の意味を知っている子」と「知らない子」では、理解度に大きな差が出ます。
特に入試では「誰もが解ける簡単な語彙」ではなく、「多くの子が迷いやすい言葉」が出題されます。
- 入試頻出の語彙(抽象的な表現、慣用句など)
- 日常では使わないような言い回し
こうした語彙をコツコツ積み重ねていくことが、安定した読解力につながります。
差がつくポイント②:記述力(自分の言葉でまとめる力)
入試で点差がつきやすいのが「記述問題」です。
- 問題文で「何を聞かれているか」を正しくつかむ
- 本文の内容を根拠にして答える
- 指定された字数に合わせて必要な情報を整理してまとめる
この3つを意識するだけで、白紙や的外れな解答が減り、点数がグッと安定します。
差がつくポイント③:読解の「型」に慣れること
国語は「センス」や「感覚」に頼る教科ではありません。実は、ある程度の「読み方の型」があります。
- 説明的文章なら「筆者の主張→根拠」
- 小説なら「登場人物の気持ちの変化」
こうした「型」を知っているかどうかで、正答率が大きく変わります。
入試までの時間は限られています。だからこそ「型を知って練習する」ことが、効率的に力を伸ばす最短ルートになるのです。
家庭でできる!2学期からの国語力アップ勉強法
国語は一夜漬けで一気に得点を一気に伸ばせる教科ではありません。だからこそ、家庭での日々のちょっとした工夫や習慣が、大きな力になります。
そこで、ここでは、親子で無理なく続けられる3つの勉強法をご紹介します。
勉強法①:語彙力アップは「親子の会話+辞書引き」でコツコツと
語彙力は読解力の土台です。実際、近年は語彙が不足している子が多く、それが読解のつまずきにつながるケースも少なくありません。
でも、特別な教材や難しい参考書を買わなくても、普段の生活の中で読解力はしっかり鍛えることができます。
- 新聞やニュースに出てくる言葉を一緒に調べる
- 読書中にわからない言葉を辞書で確認する。
- 家族の会話の中で「これってどういう意味?」と問いかける
とくにおすすめなのが、「辞書引き」の習慣です。例えば、ママやパパが問題をチェックして、「この言葉知っているかな?」と思った語句に付箋を貼り、辞書で調べたらその付箋に意味を書いてもらう方法です。子どもは自分で調べた言葉のほうがずっと記憶に残ります。
キャラクターの付箋やお気に入りの文具を使えば、お子さんの学習へのモチベーションもアップしますよ。
勉強法②:短い文章で「書く練習」をする
作文や記述対策は、実際に「書く」練習をしなければ上達しません。
とはいえ、最初から長い作文に取り組むのはハードルが高く、苦手意識を強めてしまう子もいます。
そんなときは、短い文章から始めるのがおすすめです。
- 読んだ本や記事を「3行で要約」してみる
- ニュースや出来事について「自分の意見を2~3文で」書いてみる
まずは、お子さんの興味を持ちやすいジャンルから取り組むとスムーズに続けられます。大切なのは、「書くことを日常に取り入れること」。短い文章でも、続けるうちに自然と表現力がついていきます。
勉強法③:過去問・模試を活用して「型」に慣れる
入試を見据えるうえで欠かせないのが、実際の問題形式に慣れることです。
- 地域の過去問を解いてみる
- 模試の解き直しを丁寧に行う
- 「なぜ間違えたのか」を振り返る
特に「過去問を解く」ことは、各地域の出題傾向を知るためにもとても大切です。
おすすめなのは、全国の問題を分野別に収録した『全国高校入試問題正解』シリーズ。
バリエーション豊富な問題に触れることで、「どんな文章が来ても対応できる力」を養うことができます。
国語には「読み方の型」があります。過去問や模試を通して、その型に慣れておくことが得点アップへの近道です。
親ができる“寄り添いサポート”
お子さんの受験を前に、「大丈夫かな」「もっとしてあげられることはないかな」と不安になるのは、親としてごく自然なことです。大切な我が子を想うからこそ、つい心配が膨らんでしまうんですよね。
頑張っているお子さんに対して、親として何ができるのか…。その答えのひとつは、特別なことではなく、日常の中で寄り添うことです。ここでは、親御さんだからこそできる“寄り添いサポート”をご紹介していきます。
「がんばっているね」を言葉にして伝える
子どもにとって、何より心の支えになるのは「お父さんやお母さんに認めてもらえた」という安心感です。
結果だけを褒めるとプレッシャーになってしまうこともありますが、
「今日も集中してたね」
「毎日コツコツ続けているね」
と、勉強の“過程”を言葉にしてあげると、子どもは自信を持ち、やる気を保ちやすくなります。
一緒に調べて「なるほど!」を共有する
国語の勉強では、知らない言葉に出会うのは当たり前のこと。そんなときに、ただ答えを教えるのではなく、一緒に辞書で調べて「なるほど!そういう意味なんだね」と共感してあげると、学ぶことが前向きな体験に変わります。
「勉強については学校や塾で任せたい」という気持ちも、忙しい毎日の中では当然思うことですよね。そんな気持ちもよく分かります。
でも、ほんの5分でもいいんです。週に数回、一緒に辞書を引いたり、調べたりするだけで、「親と一緒に考えた時間」が子どもにとって安心とやる気につながっていきます。
「結果よりプロセス」を大事に見守る
どうしてもテストの点数や合否が気になってしまうのは親心。でも、本当に大切なのは「今できることを少しずつ積み重ねている」というプロセスです。
「点数が上がったね!」ではなく、
「記述問題をたくさん書けるようになったね」
「古文の文章が前より読めるようになったね」
と、具体的な成長に気づいて声をかけてあげると、子どもは自分の努力が認められたと感じ、安心して挑戦を続けられます。
2学期からの勉強法で国語はまだまだ伸びる!
国語は、これからの学びや生活の土台になる大切な力を育ててくれる科目です。
- 語彙力を少しずつ増やすこと
- 短い作文や要約で書く習慣をつけること
- 過去問や模試を通して「型」に慣れていくこと
これらはどれも特別な勉強法ではありません。でも、毎日の小さな積み重ねが確実にお子さんの力となっていきます。
正直に言うと、私も中学生の頃は勉強が大の苦手でした。中学3年生のとき、入試に向けて毎日塾に通うのがつらくて、勉強への拒否反応で蕁麻疹が出たこともあります(笑)
でも、毎日少しずつ努力を積み重ねたおかげで、国語教師として働くこともできました。そして、決して立派な親ではありませんが、親として子どもと向き合うことの大切さは身にしみて感じています。
だからこそ、親御さんにできることは、やっぱり「そばで温かく見守ること」。
結果だけにとらわれず、「今日こんなことができたね」「ここまで頑張ったね」と、努力のプロセスを認めてあげてください。小さな成長を一緒に喜ぶことは、親御さんにしかできないサポートだと思います。
受験は長いマラソンのようなもの。ときには、息抜きも必要です。親子で励まし合いながら、少しずつ前に進んでいけば、必ずゴールにたどりつけます。
だから、「今日もよく頑張ったね!」と笑顔で声をかけてあげてください。その一言が、お子さんにとって何よりの力になるはずです。
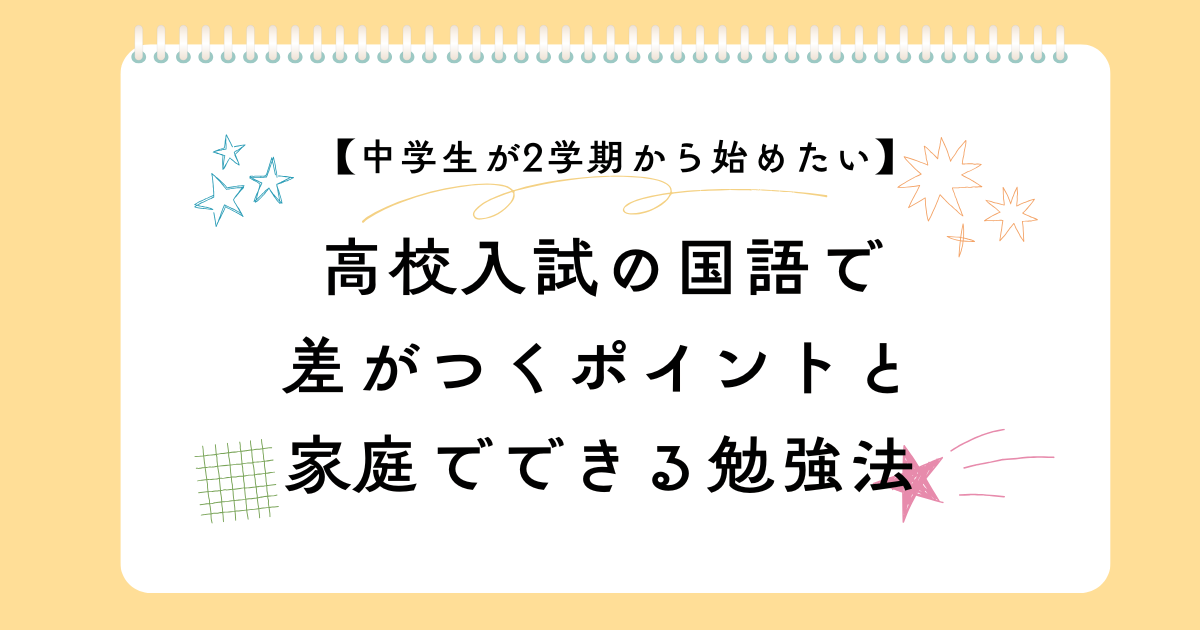
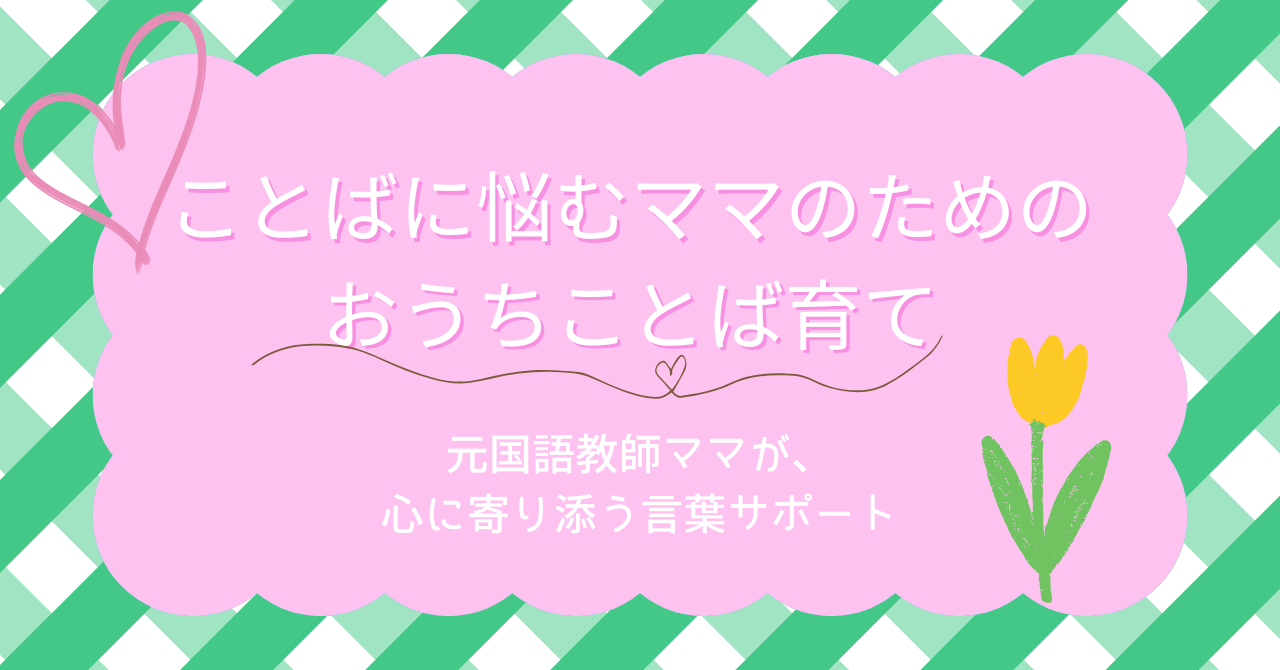
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c29180e.d28787e7.1c29180f.bc7ec557/?me_id=1213310&item_id=21606045&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2553%2F9784010222553_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

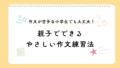
コメント